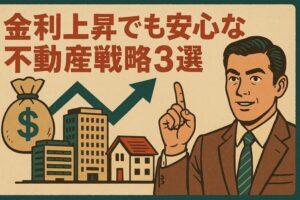現場で「最近、あの人すぐに疲れているな…」と感じる作業員がいたとしたら、あなたはどこに原因を求めるでしょうか?体力の問題、年齢の問題、やる気の問題など、多くの場合はそういった“見える”要素に目が行きがちです。
しかし近年の神経科学や労働生理学の知見では、疲労の原因は“脳の過負荷”にあるという指摘が増えています。特に繰り返し行う単純作業や、情報量の多いマルチタスクの現場では、見えない「脳疲労」が蓄積しやすくなるのです。
この記事では、現場で起きる「疲れやすさ」の本質に迫りながら、手順や設計ミスがどう脳負担を高めているのかを探っていきます。

1.作業員の疲労は脳から始まる?
「ちゃんと休憩してるのに、全然疲れが抜けない」という声が作業員から上がったとき、単なる“気のせい”として見過ごしていませんか?
従来、疲労の正体は「筋肉の疲れ」「酸素不足」といった肉体的なものとされてきましたが、近年の研究ではそれだけでは説明できないケースが多く報告されています。特に注目されているのが、「脳疲労(MentalFatigue)」という概念です。
脳疲労とは、情報処理を司る前頭前野や頭頂葉といった部位に負荷がかかり、判断力や集中力が著しく低下した状態を指します。長時間の注意集中や、複雑な判断、同時進行の作業が続くことで、脳内の神経ネットワークはオーバーヒート状態に陥ります。
とりわけ作業員が日常的に抱える問題としては、次のような要素が影響します。
- 作業手順が曖昧で、毎回の判断に迷いが生じている
- 工程ごとの注意点が多く、脳がマルチタスクに追われている
- 作業者が何度も「考え直し」や「やり直し」に直面している
これらは一見すると慣れや経験で解決できるように見えますが、実は設計段階から脳に過度な負担を強いている可能性があるのです。
また、国立保健医療科学院やアリナミン製薬の報告でも、脳疲労は「休息や睡眠だけでは回復しにくい」ことが指摘されています。つまり、疲れの根本原因を見誤ると、何度休んでも改善されない悪循環に陥るということです。
「本人の問題」として片付けるのではなく、「脳にとってやさしい作業設計とは何か?」を問い直すことが、疲労軽減の第一歩になるでしょう。
2.見えない負担「脳疲労」とは何か
では、そもそも「脳疲労」とはどのように発生するのでしょうか?その鍵を握るのは、私たちの脳内にある3つの主要ネットワークです。
2-1.DMN・CEN・SN、脳の三大ネットワークの乱れ
1つ目はDMN(デフォルト・モード・ネットワーク)で、ぼんやりしているときに働く脳の休息回路です。
2つ目はCEN(中央実行ネットワーク)で、論理的思考や意思決定を担う指令センターのことです。
3つ目はSN(サリエンス・ネットワーク)で、外的刺激に注意を向ける切り替えスイッチを刺します。
これらのネットワークは、バランスよく機能しているときに最も効率的な脳活動が行えます。しかし、作業が過度に連続したり、次々と指示や変更が飛び交うような環境では、CENばかりが酷使され、DMNに切り替える“脳の休憩時間”が確保できません。
その結果、脳は情報処理の許容量を超えてエネルギー切れの状態に陥ります。
例えば、「判断ミスや手順の飛ばし」、「誤操作の増加」、「注意力の低下によるケガや事故」、「作業へのモチベーション低下やイライラ感」などの症状が起きます。
これらは「気のせい」ではなく、脳神経回路そのものが疲弊しているというメカニズムが、科学的にも裏付けられてきたのです。
こうした“見えない負担”を放置したままでは、個人の問題に見えていた作業ミスや疲労感が、やがて組織全体の生産性や安全性に影響を及ぼす可能性すらあります。
3.“手順ミス”の裏にある情報過多
現場でよく見られるヒューマンエラーといえば、手順の抜け、順番違い、操作ミスが挙げられます。これらが起きるたびに「もっと丁寧にやれ」と注意が飛ぶこともあるでしょう。しかし本当に、これは作業員の注意力の問題だけなのでしょうか?
実は、手順の設計そのものが脳への過負荷を生んでいるケースが少なくありません。
たとえば、一つの作業フローに複数の判断工程や例外処理が含まれている場合、作業者は逐一“脳内会議”を強いられます。「この部品は今日はA処理、でも昨日はBだったな」「こっちは温度管理が必要だったはず」といった細かい判断が積み重なるほど、脳の実行機能(CEN)は疲弊していきます。
また、チェックリストやマニュアルがあっても、その項目数が多すぎたり、ページをまたいで確認が必要だったりすると、脳は「記憶」「切り替え」「再構築」の負荷を一度に背負うことになります。
このような“情報過多状態”は、脳にとって最も効率が悪く、エラーを誘発しやすい環境です。ミスが多発する作業や、特定の人が極端に疲れやすい作業には、こうした“手順の見えない負荷”が隠れている可能性を疑うべきでしょう。
たとえばある食品製造工場では、同じ材料を使うにも「午前中はAレーンで加熱→冷却→計量、午後はBレーンで逆順」という運用がされていました。この切り替えが日によって変わるため、作業者は手順を毎回再確認する必要があり、結果として「加熱忘れ」や「逆順処理」などのヒューマンエラーが発生していました。これは作業者の怠慢ではなく、認知的負荷が高すぎる手順設計が引き起こした構造的な問題だったのです。
こうした事例に共通するのは、判断を求められる場面の多さ=脳の疲労リスクです。特に「作業ミス原因」「ヒューマンエラー対策」といった視点で見直すなら、「どこで人の判断に頼りすぎているか?」という問いが極めて重要になります。情報を減らす、順番を固定する、判断不要にするなとして、現場における“脳負担のダイエット”ともいえる改善アプローチを行いましょう。
4.脳負荷を可視化する評価手法
では、どうすれば“脳に負担をかけない手順”を設計できるのでしょうか?その鍵となるのが、脳負荷の「見える化」です。
近年、労働安全や人間工学の分野では、作業中の脳疲労を測定・評価する技術が進化しています。
たとえば、「心拍変動(HRV)による交感神経・副交感神経のバランス測定」、「作業時の眼球運動やまばたき頻度の測定」、「アンケート方式による主観的疲労度評価(NASA-TLXなど)」などの手法が挙げられます。
これらの指標をもとに、「どの手順で脳が疲れているか」「どの作業が過剰な集中を要しているか」を明らかにすれば、手順改善のポイントが浮き彫りになります。
チェック項目の簡素化や判断の自動化、視覚的ガイドの追加など、脳にとって親切な設計は、人にも優しい設計です。
5.まとめ
疲れやすい作業員を「体力がない」「やる気が足りない」と切り捨てる前に、ぜひ見直してほしい視点があります。それは、「作業の手順設計が、無意識のうちに脳に負担をかけていないか?」という問いです。
脳疲労は見えないために軽視されがちですが、蓄積すればパフォーマンスの低下や事故、離職につながる重大なリスクとなります。しかも、いくら休憩や睡眠を取っても、負担の元である作業手順が変わらなければ疲労は繰り返されるだけです。
そのためには、脳への負担を評価・見える化し、工程の組み方を見直すことが不可欠です。
参考文献
- アリナミン製薬「脳疲労とは?休んでも疲れがとれない、集中力が続かない理由」
https://alinamin.jp/tired/brain-fatigue.html - からだケアナビ「気づかないうちに進む『脳の疲れ過ぎ』にご用心」
https://www.karadacare-navi.com/tips/29 - J-STAGE「作業中の休憩時間設定による身体的作業負荷パターンの違い」
https://www.jstage.jst.go.jp/article/sangyoeisei/52/1/52_B9011 - 労働者健康安全機構(ジョハス)「疲労の蓄積とその対応」
https://johas.go.jp/Portals/0/data0/sanpo/sanpo21/pdf/114_p14-17.pdf - note「【生産性向上】脳疲労によるパフォーマンスへの影響と対策」
https://note.com/boscht/n/ncfe55649ec64 - J-STAGE「頭脳労働者の自覚症状について」
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jje1965/25/Supplement/25_Supplement_152/_pdf