「夢のお店を持ちたい」という思いを抱いたとき、最初に立ちはだかるのが「お金」の壁です。勢いだけでは乗り越えられないこの壁をどう越えるかが課題となるでしょう。
大切なのは、しっかりとした資金計画と、無理のない資産運用の考え方です。
本記事では、これからお店を始める人のために、自己資金の準備から融資の活用、クラウドファンディングや補助金の使い方まで、開業前に押さえておきたい資金と運用の基本を解説します。店舗を持つ前に読んでおきたい実践的な内容をギュッとまとめています。
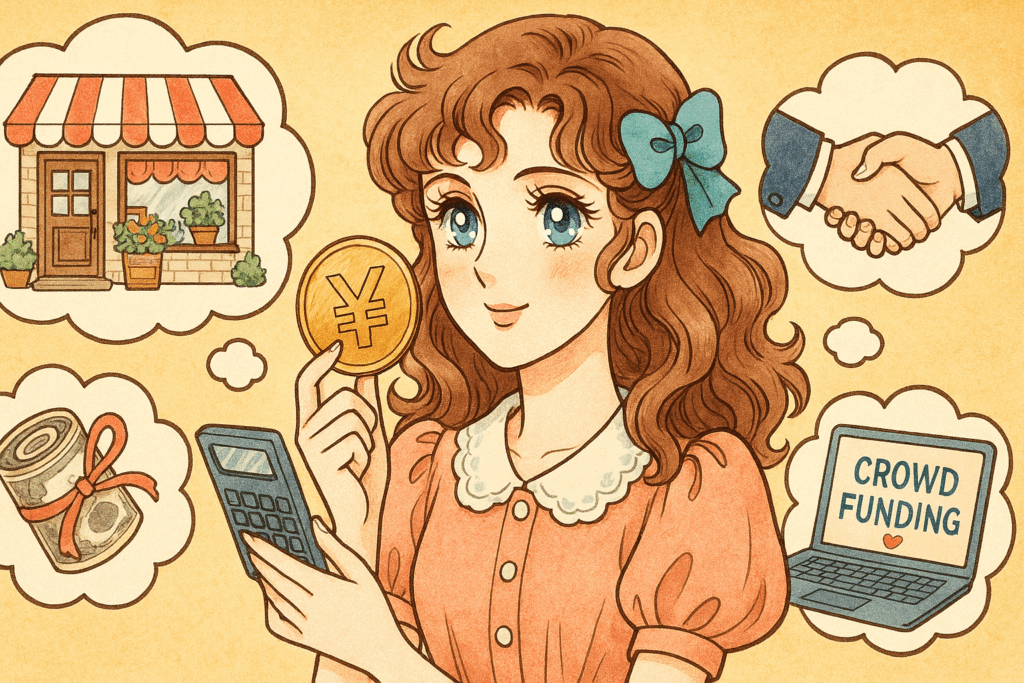
1. 自己資金の大切さとその貯め方
1-1. 自己資金は融資の信頼にも直結する
自己資金があるかどうかは、金融機関にとって大きな判断材料となります。日本政策金融公庫によると、自己資金の平均的な比率は約30%です。この割合が少ないと融資が通りにくくなる傾向にあります。融資元としては、申請者が「リスクを背負う覚悟があるか」「経営に本気で取り組む姿勢があるか」を見ています。
仮に開業資金が600万円であれば、200万円前後の自己資金が望ましいということになります。もちろん、すべて自己資金でまかなえるなら理想ですが、現実には融資と併用する形が多くなるでしょう。その際の信頼材料になるのが、この自己資金の存在です。
1-2. 自己資金をコツコツ貯める王道の方法
貯金は地味ですが、確実に自分の信用を積み上げる行為です。なかでも「収入-貯蓄=支出」の意識を持つことが鍵になります。たとえば3年で200万円を貯めるなら、毎月5.5万円前後を先取りで貯金する仕組みをつくることが大切です。
さらに、実際に資金を貯める過程で得られる「やりくり力」や「計画力」は、経営者としての基礎体力にもなります。毎月の家計簿を見直すことで、どこに無駄があるか、自分が何にお金を使いやすいかを知ることができます。
もしも支出が多くて貯金が難しいという場合は、まず「固定費の見直し」を検討しましょう。スマホの料金プランやサブスクサービスなど、意外と見逃している出費を減らすことで、毎月の可処分所得を増やせる可能性があります。金融機関もこのような地道な努力を重視しているため、開業資金の準備段階から誠実に取り組むことが信頼につながります。
2. 資金調達の種類と組み合わせ方
2-1. 融資の基本と公的支援の活用
創業融資の定番といえば「日本政策金融公庫」の制度です。特に「新創業融資制度」や「中小企業経営力強化資金」などは、金利が低く、創業初期の負担が軽減されます。金融機関によっては、保証協会を通じた信用保証付き融資もありますが、審査が長引く傾向にあるため、公庫との並行活用が有効です。
いずれの融資も、審査では事業計画書の内容が重要視されます。売上予測・費用計画・返済計画が現実的かつ筋が通っているかが問われます。また、金融機関との面談では、過去の職歴や開業動機も評価対象となるため、事前に想定問答を用意しておくと安心です。
2-2. 助成金・補助金の活用は計画的に
助成金・補助金は、返済の必要がない点で非常に魅力的です。代表的な制度としては「小規模事業者持続化補助金」や「IT導入補助金」があり、設備投資や集客支援など、幅広い使い方が認められています。
ただし、多くの制度が「後払い方式」であるため、あらかじめ資金を支出したうえで申請し、のちに補填される仕組みです。このため、自己資金や融資との併用を前提としたスケジュール管理が求められます。
さらに、申請書の作成には一定の知識が必要です。書類の整合性や必要書類の不備があると、不採択となることもあります。申請前には、専門家(認定支援機関など)にチェックを受けるのが賢明です。
最近では、申請代行を行う士業やコンサルタントも増えているため、そうした専門家の支援を受けることで採択率を高めることが可能です。
2-3. クラウドファンディングで共感を資金に変える
共感を資金に変える方法として注目されているのが「クラウドファンディング」です。特に「購入型クラファン」は、リターンとして自社商品やサービスを提供することで資金を集めるスタイルで、飲食業とも相性が良いでしょう。
たとえば、オープン前のプレイベント招待券や限定メニュー、オリジナルグッズなどを提供することで、未来のファンとつながることができます。成功するクラウドファンディングの多くは、「なぜそのお店をやりたいのか」という物語を丁寧に発信している点が共通しています。
SNSとの連携も重要です。支援者に対して進捗状況をこまめに共有することで、信頼と期待感を高められます。開業前から顧客基盤を育てられるという点でも、大きなメリットがあります。
一方で、クラファンは「成功しなかった場合のリスク」も潜んでいます。資金が集まらないとプロジェクト自体が立ち消えになる可能性があるため、あらかじめリターンの設計やスケジュールの検証が不可欠です。
3. 開業後の資産運用も見据えて
3-1. 店舗経営と家計の資金を切り分ける
開業後は、事業用資金と個人の生活費を明確に分けて管理することが大切です。とくに初期の段階では、売上が不安定になりがちなため、生活費をミニマムに抑える覚悟も求められます。
事業と家計がごちゃまぜになると、キャッシュフローの見通しが甘くなり、知らぬ間に資金繰りが逼迫するリスクがあります。可能であれば、生活防衛費として3〜6ヶ月分の生活費を別口座にプールしておくと安心です。
このような資金管理の徹底が、長期的な経営安定につながります。
3-2. 余剰資金は『貯める』『運用する』のバランスを取る
事業が軌道に乗り、手元に余剰資金が出てきた場合、そのお金をどう活かすかも重要な経営判断です。「すぐに使わないから銀行に寝かせておく」だけでは、インフレによる実質的な目減りリスクがあります。
このときに考えたいのが「余剰資金の資産運用」です。たとえば、法人名義での定期預金やMMF(マネー・マネジメント・ファンド)、安全性の高い社債などを活用することで、リスクを抑えつつ利回りを確保できます。
また、事業内容と親和性のある設備投資や、新サービス開発への再投資も選択肢の一つです。運用益を追求するだけでなく、自社の成長に還元することで、資金が生きた使い方になります。
ただし、資産運用には当然リスクも伴います。事業資金と運用資金を混同せず、必要な運転資金を確保したうえでの余剰分のみを運用するルールを徹底しましょう。
まとめ
自分のお店を持つためには、夢だけでなく「お金」と現実的に向き合うことが欠かせません。自己資金の準備、融資や補助金の活用、共感を集めるクラウドファンディング、そして開業後の資金管理や資産運用まで。ひとつひとつの選択が、店舗経営の土台となります。焦らず、着実に準備を重ねていくことで、理想のお店を現実のものにできるでしょう。お金の不安を希望に変える力は、正しい知識と行動から生まれます。
参考文献
- 飲食店経営で知っておきたい資金調達のポイントと方法|経営支援コラム
https://ozaki.osaka.jpnote.com - 起業前の資金繰りでスタートダッシュ|ショウ(note記事)
https://note.com/sho_startup - 始める前に覚えたい、飲食店経営における開業資金の集め方|K‑BOX
https://k-box.jp/startup-funding/ - 自己資金を効率よく貯める方法 基本編|飲食店ちょい足しコラム
https://cdc-office.jp/column/save-fund/ - 日本政策金融公庫の創業計画書の書き方(数字計画完全版)|飲食店開業支援ブログ
https://y-itax.com/startup-plan-guide/ - 法人の余剰資金の資産運用【中小企業編】|起業家バンク
https://entrebank.jp/corporate-investment/ - 基礎から学べる投資の鉄則(金融庁PDF)
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/assets/pdf/learning_rules.pdf





