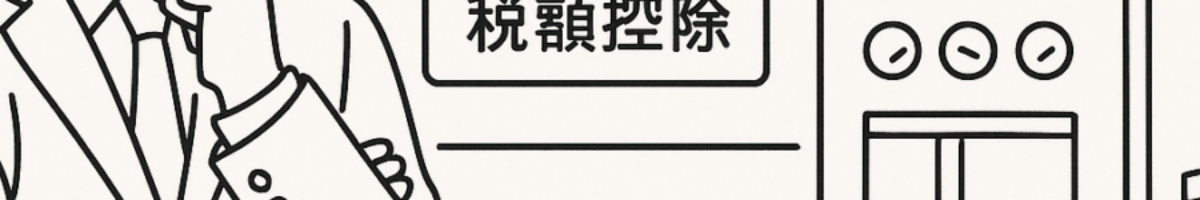中小企業投資促進税制は、一定の設備投資を行った中小企業に対し、初年度に特別償却または税額控除を認める制度です。通常の減価償却では数年に分けて経費化する設備費用を、一度に費用化できるため、法人税の負担を大幅に軽減できます。
しかし、適用要件や手続きには細かなルールがあり、準備不足で思わぬ不利益を被るリスクも存在します。本記事では、制度の仕組みから計算方法、落とし穴と対策、申請手続きまでをわかりやすく解説します。

1.投資促進税制の仕組みと対象要件を解説
1-1.制度の目的と基本概要
中小企業投資促進税制は、設備投資を活性化し、生産性向上を目的としています。取得価額の30%の特別償却、または税額控除(取得価額の7~10%)のどちらかを選択でき、導入コストを早期に回収可能です。
適用対象は「業務用機械装置」「器具備品」「建物附属設備」などで、原則として国内で新規に取得・設置されたものに限られます。
加えて、2024年度の実績では中小企業1万社超が本制度を利用し、平均投資額は約1,200万円、平均節税額は約150万円に上ったという経済産業省の報告もあります。
特に製造業やIT関連企業で導入が活発で、IoT対応機器や省エネ設備への投資が増加傾向にあります。導入前にリース契約や融資条件を十分比較し、キャッシュアウトのタイミングを正確に把握しておきましょう。
1-2.適用要件のチェックポイント
中小企業投資促進税制を正しく利用するための主なチェックポイントは次の通りです。
- 適用対象者
青色申告書を提出する中小企業者等のうち、個人事業主の場合は「常時使用する従業員数1,000人以下」、法人の場合は「資本金3,000万円以下」である必要があります。所得金額や大企業の子会社(出資比率)等で適用除外となる場合もあります。 - 対象設備の要件
取得した資産が以下のいずれかに該当する新品設備となります。- 機械装置:1台あたり取得価額160万円以上
- 測定工具・検査工具:1台120万円以上(30万円以上×4台の場合でも可能)
- ソフトウェア:1本70万円以上(複数合計70万円以上の場合でも可能)
- 貨物自動車:車両総重量3.5トン以上のもの
中古品の扱いや転用設備(M&Aで引き継いだ機械など)の可否は例外規定が複雑なため、申請前に税理士など専門家へ必ず確認しましょう。
2.節税効果の計算方法とメリットを検証
2-1.特別償却と税額控除の比較
取得価額1000万円の機械装置を例に、30%の特別償却を適用した場合、初年度に300万円を損金計上できます。一方、税額控除を選ぶと、仮に控除率10%なら100万円の法人税額を直接減額できる仕組みです。
特別償却と税額控除の選択基準のポイントは、「当期の課税所得状況(前年実績との比較)」、「キャッシュフロー予測(資金繰り表の見直し)」、「事業計画の利益見込み(5年単位でのROI試算)」などがあります。
特別償却は早期に損金を計上できるため、赤字転落リスクが低い場合に有効です。一方、黒字幅が大きく、税負担を先に圧縮したい場合は税額控除が有利でしょう。
2-2.実際のメリット試算
設備投資による節税効果と生産性向上のキャッシュフロー改善を、具体的な数字で見てみましょう。以下の前提で比較します。
①投資金額1,000万円
②法人税率30%
③特別償却率30%
④税額控除率7%
| 計算式 | 節税額 | |
| 特別償却 | 投資額1,000万円×特別償却率30%=300万円を経費計上 →300万円×税率30%=90万円の税金減 | 90万円減 |
| 税額控除 | 投資額1,000万円×税額控除率7%=70万円を税金から直接控除 | 70万円減 |
特別償却は、設備取得年度に300万円を経費として利益から差し引けるため、税金は90万円減ります。
税額控除は、取得年度の税額から70万円をそのまま割り引けます。
3.活用時に陥りやすい落とし穴と対策
3-1.対象要件の誤解による適用漏れ
すべての事業用設備が対象になるわけではなく、ソフトウェア単体や社用車、リース品は適用対象外です。
導入前に国税庁の要件をチェックし、設備仕様書をもとに専門家へ確認したほうが良いでしょう。また、DX投資促進税制の特例設備(クラウド利用料含む)との重複適用をお考えの場合も確認するべきポイントとなります。
3-2.書類不備による申請差し戻し
見積書と領収書、減価償却資産の明細書の金額や日付にずれがあると、申請が差し戻されます。申請用フォーマットを活用し、部署横断の二重チェック体制を整えましょう。
実際、某製造業の事例では、領収書の宛名が異なっていたため申請が再提出となり、数十万円の適用タイミングが遅延しました。
3-3.キャッシュフローへの影響を見誤るリスク
初期投資額は一時的に支出となるため、資金繰り計画を伴わない設備導入は手元資金を圧迫します。国や地方自治体の助成金、設備ローンを組み合わせ、分割で支払う等の検討も必要です。
4.申請手続きの流れと事前準備のポイント
4-1.確定申告で扱う申請の流れ
中小企業投資促進税制を利用する際、まず押さえておきたいのは「設備を取得して1年以内に事業に使用する」「取得後すぐに支払いを完了する」の2点です。
取得から使用開始、そして支払いのタイミングが要件から外れると適用できませんので、資金計画には余裕をもって臨んでください。
実際の申告では、法人税の確定申告書(電子申告のe-Taxまたは書面)に特別償却や税額控除の欄を記入します。投資額や償却率、適用を希望する控除額などを正確に記載することが極めて重要で、税務署の審査で確認されるポイントとなります。
助成金のような「交付通知」は発行されないため、この申告手続き自体が適用申請となります。
4-2. 重要な証拠書類の準備と管理
申告時には、設備取得の証拠となる見積書や請求書、領収書をまとめるだけでなく、実際に設備が稼働している資料も用意しておくと安心です。
具体的には、設備の仕様概要や導入直後の設置状況がわかる写真、社内で使用を開始した日付がわかる運用記録などが該当します。
これらの証憑は法人税の申告書に添付する明細書類として提出し、後日の税務調査でも重要視されます。
国税庁のガイドラインでは、申告書類は7年間の保存が義務付けられているため、スキャンデータなど電子データで保管すると管理がスムーズです。必要なときにすぐ参照できるようにしておきましょう。
5.まとめ
中小企業投資促進税制は、初年度に高い損金算入や税額控除を受けられる強力な節税策です。一方で、適用要件の誤解や書類不備、資金繰りの甘さといった落とし穴があります。
専門家の助言を受けつつ、自社の利益構造とキャッシュフロー試算を踏まえた上で、正確な手続きと無理のない投資計画が必要になります。効果的な節税と次なる成長投資への原資確保を同時に実現できますので、ぜひ活用ください。
参考文献
国税庁「No.5433中小企業投資促進税制(機械等を取得した場合の特別償却・税額控除)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htm
freee「中小企業投資促進税制とは?対象設備や申請に必要な書類について」
https://www.freee.co.jp/kb/kb-erp/sme_investment_promotion_tax_system/
あいせ税理士法人「中小企業投資促進税制を活用しよう!具体的活用方法について解説」
https://ayse-tax.com/column/20230403-3/
マネーフォワードBiz「買い替えの方がお得!?中小企業投資促進税制を使って賢く設備投資する方法」
https://biz.moneyforward.com/accounting/basic/13318/
京セラ「中小企業経営強化税制・中小企業投資促進税制を活用した太陽光発電導入」
https://www.kyocera.co.jp/solar/support/topics/r5-zeisei/