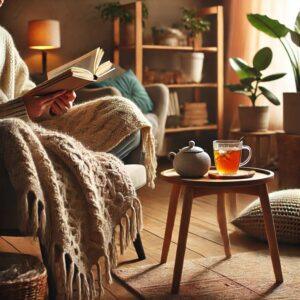築年数が古くなると、賃貸物件としての価値が下がると考える人も少なくありません。実際、「築30年=空室リスクが高い」というイメージを持たれがちです。しかし、現実には築30年を超えても稼働率90%を維持している物件が存在します。その背景には、単に建物の新しさでは測れない「立地の力」があります。
この記事では、築古物件でも高稼働を維持する理由、そして見落とされがちな立地条件の真実について、実例を交えて解説します。投資初心者やこれから物件購入を考えている方にとって、目から鱗の情報になるはずです。
1. 築30年でも高稼働を保つ物件の特徴
築年数が経過していても、空室が少なく稼働率が高い物件には共通点があります。1つは、適切なメンテナンスやリフォームによって建物の外観や室内設備が一定水準以上に保たれていることです。もう1つは、ターゲットとする入居者のニーズを的確に捉えている点です。
とくにファミリー層をターゲットとする物件では、間取りが広めで、周辺に教育施設や買い物施設があるなど「暮らしやすさ」が重視されます。築30年であっても、定期的な修繕により快適性が維持されていれば、入居希望者は絶えません。
また、住宅設備においても、古いタイプの給湯器やトイレを最新の省エネ仕様に更新することで、光熱費を抑えたい入居者からの好感度が上がります。さらに、インターネット無料や宅配ボックスの設置など、現代のライフスタイルに対応した工夫が施されている物件は、築年数に関わらず選ばれる存在となり得るのです。
2. 見落とされがちな“立地条件”とは
物件選びで「駅近」や「商業施設の充実」といった条件はよく注目されますが、実際にはそれだけでは十分とは言えません。築古物件が高稼働を維持するためには、以下のような“見落とされがちな立地要素”が大きく関係しています。
物件選びにおいて、「駅からの距離」や「商業施設の利便性」といった条件に注目する方は多いですが、築古物件を高い稼働率で運用していくためには、もう一歩踏み込んだ立地選びが求められます。特に見落とされがちなのが、生活者目線での“安心・安全”や“快適さ”に関する要素です。
たとえば、小学校や中学校への通学距離が近いことは、子育て世帯にとって非常に魅力的です。毎日の通学が負担にならない立地であれば、長く住んでもらえる可能性が高まります。
また、騒音の少ない住宅エリアであることも、住み心地の良さにつながります。幹線道路や繁華街に近すぎると騒音トラブルの原因になりやすく、敬遠される傾向があります。
さらに、防災や医療の観点から、近隣に避難所や医療機関があるかどうかもチェックすべきポイントです。いざという時に頼れる施設が近くにあることは、入居者にとって大きな安心材料となります。
加えて、昼夜を問わず治安が良好であるかどうかも重要です。特にファミリー層や女性の単身入居者にとっては、安心して生活できる環境があるかが物件選びの大きな判断基準となります。
このように、築古物件の稼働率を高めるためには、利便性だけでなく、生活者目線の“見えにくい立地要素”を丁寧に見極めることが不可欠です。
これらは、日常生活における「安心・安全・快適さ」に直結する要素であり、特にファミリー層や高齢者にとっては物件選定の重要な判断基準となります。また、駅から多少距離があっても、バスや自転車でのアクセスが良好であれば十分に需要が見込めるケースもあります。
実際、駅徒歩15分圏内でも、学校やスーパー、病院が徒歩5分圏内にあるエリアでは、築古物件であっても高い稼働率を維持している事例が少なくありません。
3. 実例に学ぶ!失敗・成功の分かれ道
築30年前後の物件を購入した投資家の中には、成功例もあれば失敗例もあります。成功するケースの多くは、「立地の微差」に注目し、賃貸需要をピンポイントで捉えた戦略を採っている点が共通しています。
たとえば、ある投資家は築32年の物件を購入する際、「駅距離はあるが、保育園・公園・小児科の充実」というファミリー層向けの立地に注目し、空室を短期間で満室にしました。反対に、表面利回りの高さだけで選んだ物件が、周囲に生活インフラが少なく、リフォーム費用をかけても入居が決まらず苦戦したケースもあります。
このように、築古物件の価値は「建物そのもの」よりも、「周辺環境との相性」で大きく変動します。購入時にはGoogleマップや周辺環境の現地確認を怠らず、数字では見えない暮らしの質を見極めることが重要です。
4. 空室リスクを下げる内覧時の着眼点
物件購入の前段階である「内覧」では、見逃してはならないポイントがあります。築年数が古いからこそ、建物自体の状態に加えて、以下のような細部を確認することが重要です。
- 雨漏りやひび割れなど構造的な劣化の有無
- ゴミ置き場や共有スペースの清潔さ
- 周辺住民の生活音や治安の肌感覚
- 外灯や街路樹など、夜間の安全性の確保
これらのチェックポイントは、実際の生活に直結する要素であり、入居者満足度を左右します。築古物件に対する不安は、細かい確認と対策で解消できるケースも多く、適切な対応で空室リスクを軽減できるのです。
5. 築古物件を資産として活かす発想を
築年数をネガティブに捉えるのではなく、「今あるストックをどう活かすか」の視点に切り替えることが、投資成功の鍵です。新築志向が根強い日本においても、海外では築100年を超える物件が資産として大切にされている例もあります。
たとえば、地域との結びつきを深めることで、住民に愛される物件に育てる取り組みが注目されています。地域イベントへの協力や、共用スペースに掲示板を設けて地域情報を発信することで、住み心地の良さだけでなく、周囲とのつながりも評価ポイントにです。
また、近年ではリノベーション物件の人気も高まっており、「古くてもオシャレ」「設備は最新」といった印象を与えることで、競合物件との差別化が図れます。築30年という数字だけにとらわれず、ポテンシャルを活かす工夫が求められているのです。

6. まとめ
築30年を超える物件でも、稼働率90%以上を維持することは十分に可能です。その鍵となるのは、単なる「駅近」だけでは語れない立地条件や、物件自体のメンテナンス状況、そして入居者の暮らしを見据えた設備の工夫にあります。
築古だからダメという考えを捨て、立地や生活環境に目を向けることで、むしろ割安で価値ある投資が実現できます。重要なのは「誰にとって暮らしやすいか」を見極め、物件と地域の魅力を最大限に引き出す視点です。
参考文献
築30年マンションで後悔したこと10選!今から買っても大丈夫?
築30年マンション購入を検討してから物件Sに落ち着くまでの道のり
築30年が狙い目?プロも注目の意外なメリット
築30年の中古マンションは買っても大丈夫?後悔しないための注意点
築30年中古住宅で後悔しない!賢い選び方と対策。失敗談から学ぶ完全ガイド
築40年超の古いマンションってあと何年住める?注意点や考え方を解説