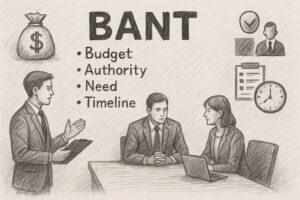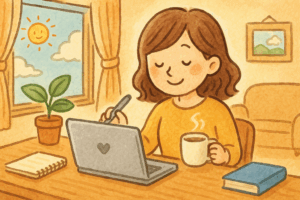住まいは人生で最も大きな買い物のひとつですが、「住みながら稼ぐ」という新たな選択肢が注目されています。それが「住宅兼賃貸」、つまり自宅の一部を他人に貸し出すことで家賃収入を得る仕組みです。従来のマイホームとは違い、住宅ローンの返済に家賃収入を充てることができるため、家計の負担を軽減しながら資産形成も可能になります。
本記事では、住宅兼賃貸の基本的な仕組みやメリット、導入時の注意点、成功のポイントまでを具体的に解説します。これからマイホームを検討する方や、不動産投資に興味がある方にとって、新しい暮らしとお金の両立術となる内容です。

1.住宅兼賃貸とは?仕組みを解説
1-1. 賃貸併用住宅の基本構造
住宅兼賃貸、または賃貸併用住宅とは、ひとつの建物の中に「自分の居住スペース」と「第三者へ貸し出す賃貸スペース」の両方を備えた住宅のことを指します。たとえば、1階部分を賃貸にし、2階を自宅とするスタイルや、玄関が2つある二世帯住宅のような設計が一般的です。
自宅と賃貸部分が明確に分かれていることで、プライバシーを確保しながら家賃収入を得られる点が大きな特徴です。また、住宅ローン控除の適用を受けるには「自宅部分が全体の50%以上」などの条件があるため、設計段階での配慮が重要になります。
1-2. ローンと税制の関係
住宅兼賃貸では、住宅ローンの利用が可能ですが、条件を満たす必要があります。自宅部分が50%以上を占めていれば、通常の住宅ローンが適用され、金利の優遇や住宅ローン控除の恩恵も受けられます。
一方、賃貸部分については「不動産所得」として税務申告が必要です。収入と経費のバランス次第で節税につながる可能性もあります。たとえば、減価償却や修繕費、管理費などを経費計上することで、所得税や住民税の負担を軽減する効果も期待できます。
2.賃貸併用住宅の5つのメリット
2-1. 住宅ローンの返済負担が軽くなる
最大のメリットは、賃貸部分の家賃収入で住宅ローンの一部または全額をまかなえる点です。たとえば月額8万円の家賃収入があれば、年間で96万円の返済負担を軽減できます。これにより、家計の固定費が抑えられ、将来的な資産形成にもつながります。
2-2. 初心者でも始めやすい不動産投資
住宅兼賃貸は、不動産投資のハードルを下げてくれます。自分が住む物件の一部を貸し出すスタイルなので、収支の見通しが立てやすく、空室リスクや物件管理の難易度も比較的低くなります。不動産投資に不安を感じている方でも、段階的に経験を積めるのが大きな魅力です。
2-3. 所得税・住民税での節税が可能
賃貸部分の収入と経費は確定申告によって「不動産所得」として処理されます。この際、減価償却費や固定資産税、ローンの利息部分、修繕費などを経費として計上できるため、所得税・住民税を軽減できるケースがあります。将来的な税金対策としても有効です。
2-4. 自宅の資産価値が高まりやすい
賃貸併用住宅は、通常の自宅よりも収益性があるため、資産価値が維持されやすい傾向にあります。将来的に売却を検討する場合でも、「投資用物件」として販売できる可能性があるため、出口戦略の幅も広がります。
2-5. 生活スタイルに合わせた活用ができる
たとえば、子どもが独立した後は空いた部屋を賃貸に回す、あるいは親と同居するタイミングで賃貸部分をリフォームして使うなど、ライフステージに応じて柔軟に使える点も特徴です。こうした多目的性は、一般住宅にはない大きな利点です。
3.賃貸併用で注意すべきリスク
3-1. 空室リスクと収支のブレ
想定していた家賃収入が入らなかった場合、ローン返済が家計を圧迫するリスクがあります。地域の賃貸需要や築年数、駅からの距離、間取りなど、募集のしやすさは事前に十分リサーチしましょう。市場調査を怠ると、空室期間が長引き赤字になることもあります。
3-2. 管理やトラブル対応の煩雑さ
入居者からの騒音トラブルや修繕依頼など、大家としての対応が発生します。自宅と隣接している場合、距離が近いぶん対応が迅速に求められることもあり、精神的負担になることもあるでしょう。外部の管理会社に委託することも視野に入れておくと安心です。
3-3. ローンの条件や税制の制限
前述のように、住宅ローンの適用条件に「自宅部分が50%以上」などの制限があります。これを満たさないと金利の低い住宅ローンではなく、投資用ローン(=金利が高い)になる場合もあるため、建物の設計段階から慎重な計画が必要です。
4.成功する住宅兼賃貸のポイント
住宅兼賃貸を成功させるためには、まず「立地選び」が何より重要です。特に駅から徒歩10分圏内といった、入居希望者が集まりやすいエリアを選ぶことで、空室リスクを大きく軽減できます。生活の利便性が高く、通勤や通学に便利な地域は、賃貸需要が安定している傾向にあるためです。
また、将来的な用途変更を見据えた設計も成功の鍵となります。たとえば、自宅部分を将来的に賃貸に転用したり、逆に賃貸部分を自分の居住スペースとして活用したりできるような柔軟な間取りにしておくと、ライフステージの変化に応じた運用が可能になります。二世帯住宅やメゾネットタイプなども一例です。
さらに、税務や資金計画の観点からは、事前に税理士やファイナンシャルプランナー(FP)に相談することが非常に重要です。住宅ローンの扱いや減価償却、確定申告など、複雑な税務処理を適切に行うためには、専門家のサポートが欠かせません。知識の有無が、収益性とリスクの差となって表れるため、スタート段階からプロの助言を取り入れることが成功への近道となります。
このように、立地・設計・税務の3つの視点をバランスよく押さえることで、住宅兼賃貸という選択肢を、資産形成につながる強力な手段へと変えることができます。
5.まとめ
住宅兼賃貸は、住まいと投資を両立できる新しいライフスタイルです。賃貸収入でローン返済を軽減しつつ、将来の資産形成にもつながるメリットは非常に大きいといえるでしょう。一方で、空室リスクや管理の手間といった注意点もあるため、事前の準備と知識が重要です。正しく理解し、目的に合った運用をすれば、家計にゆとりと将来の安心をもたらす選択肢となるはずです。
参考文献
- 賃貸併用住宅とは?仕組みや収支、節税メリットをわかりやすく解説(https://alphardic.com/column/real-estate/real-estate-investment-method/)
- 賃貸併用住宅なら100万円からでも不動産投資は可能?(https://alphardic.com/column/real-estate/1-million-yen-real-estate-investment/)
- 不動産投資のメリット・デメリット(https://alphardic.com/column/real-estate/real-estate-investment-advantages-and-disadvantages/)
- 賃貸併用住宅は節税できる?税理士が解説(https://www.tohshin.co.jp/magazine/article0014.html)
- 賃貸併用住宅とは?初心者にこそおすすめの理由(https://rei-book.com/realestate-investment/beginner/)