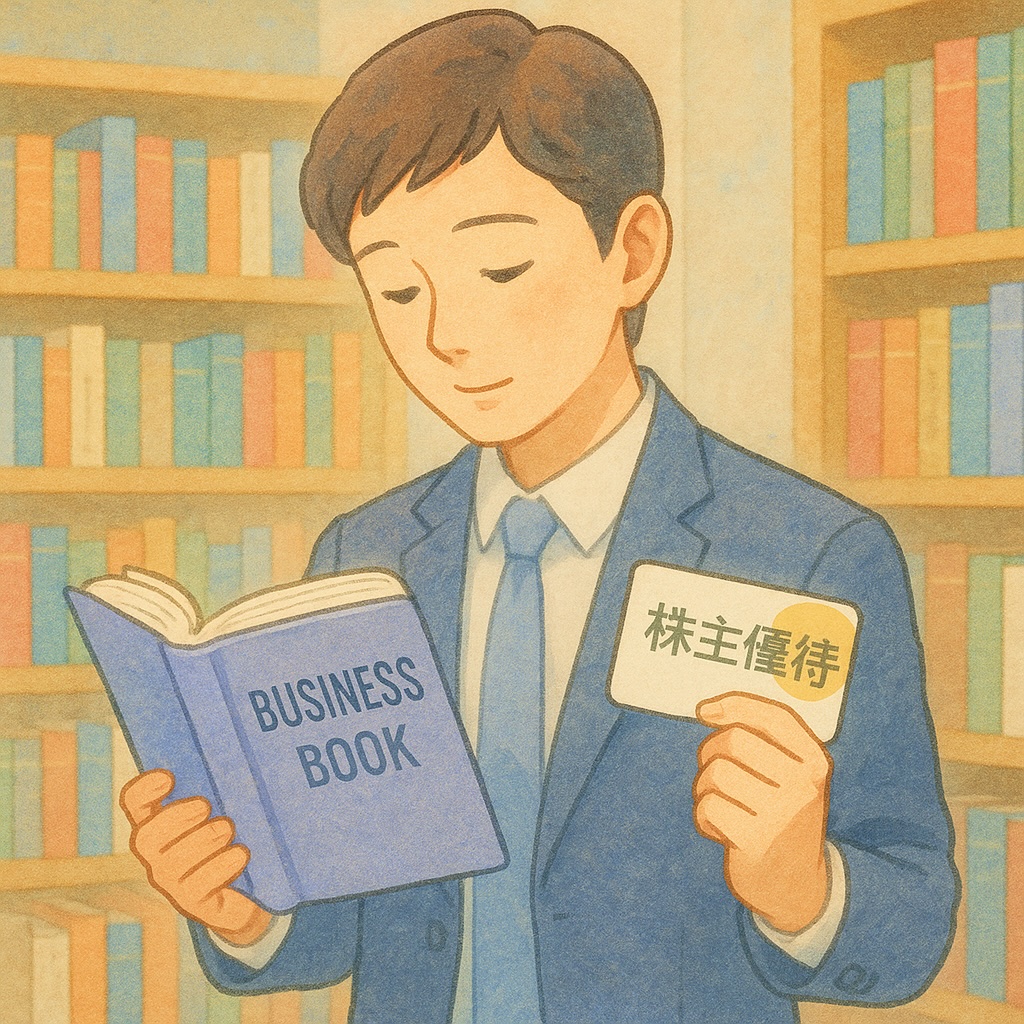
知識への投資は、成功する個人事業主やビジネスパーソンに共通する習慣のひとつです。なかでも読書は、費用対効果の高い自己投資手段として注目されています。しかし、毎月数冊のビジネス書を購入するとなると、意外と書籍代がかさむこともあるでしょう。
そこで、今回注目したいのが「書店系株主優待」の活用です。一定数の株式を保有することで、図書カードや商品券などが受け取れ、書籍代を実質無料にすることも可能です。
本記事では、自己投資に役立つ書店優待の魅力と活用方法をわかりやすく、ご紹介します。ぜひ、最後までご覧ください。
1. 書店優待を活用すれば、自己投資のコストが下がる
書店優待とは、書籍購入に使える図書カードや商品券、出版社直営サイトで利用できるポイントなどを、株主に提供する制度です。書店や出版社を運営する上場企業の株を一定数保有することで、年に1〜2回これらの優待が受け取れます。
例えば、丸善CHIホールディングス(3159)は、全国の丸善やジュンク堂書店で使える図書カードNEXTを提供しており、書籍購入に直接活用できます。また、ヴィレッジヴァンガード(2769)はユニークな優待制度で、商品券を配布しており、書籍や雑貨の購入に利用できるのが特徴です。
加えて、KADOKAWAでは、自社オンラインストアで利用可能なポイントが付与され、書籍や電子書籍の購入に使用できます。特定のジャンルに偏らず、ビジネス書や教養書、実用書などもラインナップされており、幅広い読者層に対応しています。
また、TOPPANホールディングス(7911)では、総合電子書籍ストア「ブックライブ」で使えるデジタル図書券が付与されます。デジタル優待券を活用すれば、話題の新刊ビジネス書も発売日にすぐ読むことができ、学びのタイミングを逃しません。
これらの優待制度は、読書にかかるコストを軽減しながら、定期的な知識のインプットをサポートしてくれます。しかも、個人事業主であれば、ビジネスに関係のある書籍であれば「新聞図書費」として経費計上することも可能です。
優待で入手した図書カードやポイントであっても、領収書や使用履歴を残しておけば会計処理の対象になり得ます。つまり、書店優待を活用することは、読書を単なる趣味で終わらせず、ビジネスに直結させる賢い投資手段といえるのです。
2. 読んで終わりにしない。優待本を“行動”につなげよう
株主優待で手に入れた書籍は、知識として蓄積するだけでなく、具体的な行動に結びつけることで初めて“自己投資”としての意味を持ちます。読書を通じて得た学びを実践し、自身の業務や生活に活かすことが重要です。
例えば、時間術に関する本を読んだなら、翌日から実際にスケジュール管理方法を変えてみる。マーケティングの基礎を学んだら、自身の商品やサービスのPR手法を改善してみる。小さな行動でも実行に移すことで、本の内容が記憶に定着し、結果として成果にもつながっていきます。
さらに効果的なのが、読んだ内容をアウトプットする習慣です。ブログやSNSに書評や学んだことを投稿したり、誰かに話してみたりすることで、自分の言葉で再構築できるようになります。これは、読書を知識だけで終わらせず、「考える力」や「伝える力」にも昇華させるトレーニングになります。
こうした好循環を作るうえで、株主優待は読書習慣を定期化する“きっかけ”としても有効です。優待の到着時期に合わせて「今月はこの本を読もう」と計画を立てることで、学びのペースを崩さず継続できます。丸善CHIのように年2回優待が届く企業であれば、半年に一度、自分への読書ミッションを設定するのもよいでしょう。
書店優待を賢く使えば、費用をかけずに継続的なインプットが可能になります。読んで、実践して、発信する。この3ステップを繰り返すことで、株主優待で手に入れた一冊が、人生やビジネスを大きく動かす一冊になるかもしれません。
3. 読書効果を最大化する自己投資サイクルとは
せっかく株主優待で手に入れたビジネス書も、ただ読んで終わってしまっては“知識の消費”で終わってしまいます。本当に価値ある自己投資にするためには、読書から得た知識を「実践」と「振り返り」につなげるサイクルを確立することが大切です。
まず、大切なのは、読書の目的を明確にすることです。なんとなく面白そうだから、話題だからという理由で手に取るのも悪くはありませんが、「この本から何を得たいのか」を意識することで、読書の質は格段に向上します。
例えば、「時間管理を改善したい」「SNS集客のノウハウを知りたい」など、今の自分の課題を解決することをゴールにすると、読むべきページ、メモを取るべき箇所も明確になります。
次に重要なのが、アウトプットを前提に読むことです。読み終えたあとに誰かに話す、X(旧Twitter)やnoteに要点を投稿する、自分の仕事や生活にどう活かせるかを書き出すといったアウトプットを前提にすると、自然と集中力が高まり、記憶にも定着しやすくなります。
これは「インプットの質を高める最大の方法はアウトプットである」と言われるほど、教育・学習分野でも支持されている考え方です。そして、実際に行動に移すフェーズです。どれほど良書を読んでも、現実が変わらなければ意味がありません。
例えば、営業力強化の本を読んだなら、すぐに自分の営業トークに一つでも新しい要素を取り入れてみること。文章術の本を読んだら、ブログやSNS投稿の構成を改善してみる。些細な一歩でも、自分のビジネスや日常がほんの少し変化した時、それが「読書が投資に変わる瞬間」です。
この一連のサイクルを、「読む→整理する→行動する→振り返る」として習慣化できれば、読書は自己投資としての真価を発揮します。株主優待という“無料で本が手に入る仕組み”は、このサイクルを止めずに回し続けるエンジンのような存在になってくれるはずです。
最も重要なのは、優待を「安く本を手に入れる手段」としてだけでなく、「知識を資産化する仕組みの一部」として捉えることです。読書を起点にした自己投資サイクルを回し続ければ、長期的に見て大きな成果につながることは間違いありません。
まとめ
書店や出版社が提供する株主優待は、単なる「お得な制度」ではありません。図書カードや割引、オンラインストアのポイントなど、さまざまな形で“知識の種”を手に入れる機会を提供してくれます。
丸善CHIホールディングスやヴィレッジヴァンガード、KADOKAWA、TOPPANホールディングスといった企業の優待を活用すれば、毎月数冊の書籍を実質的に無料で読める環境を構築することも難しくありません。
また、個人事業主や副業をしている方にとっては、書籍代を「新聞図書費」として経費計上できる可能性もあり、優待と節税のダブル効果が期待できます。購入費用を抑えるだけでなく、その本から得た知識をしっかりと実践に落とし込めば、それは明らかな「投資リターン」になります。
読書という行為は、地味で即効性はないかもしれませんが、確実に人の視野を広げ、行動を変え、成果をもたらす力を持っています。だからこそ、その読書を継続できる環境づくりが重要であり、株主優待という制度は、その一翼を担ってくれる有効なツールなのです。
今日から始められる「知識への投資」。あなたもまずは、書店優待を使って、自分だけの学びの循環を作ってみてはいかがでしょうか。
参考文献
- 丸善CHIホールディングス IR情報:https://www.maruzen-chi.co.jp/ja/ir.html
- 株式会社KADOKAWA IR情報:https://group.kadokawa.co.jp/ir/
- ヴィレッジヴァンガード コーポレートサイト:https://www.village-v.co.jp/
- TOPPANホールディングス IR情報:https://www.holdings.toppan.com/ja/ir/
- 日本取引所グループ(JPX):https://www.jpx.co.jp/





