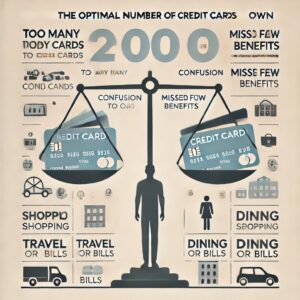近年、メーカーと消費者が直接つながるビジネスモデルが急速に拡大しています。その背景には、「中抜き」と呼ばれる中間業者の存在意義が薄れているという経済構造の変化があります。
本記事では、「中抜き崩壊」の実態と、それによって生まれたメーカー直販(D2C)という新しいビジネスモデルの全体像を、国内外の事例とともに解説します。
中小企業やスタートアップ、個人ブランドにも大きなチャンスをもたらすこの潮流を、今こそ理解しておきましょう。
1. 中抜き構造の終焉とD2Cの台頭
「中抜き」とは、メーカーから小売店に至るまでに複数の仲介業者が介在する、日本特有の多重下請け・流通構造を指します。戦後の高度経済成長を支えたこのモデルも、今ではコストや情報の遅延の元凶となり、時代にそぐわないものとなりつつあります。
一方で、インターネットの普及やECプラットフォームの進化、スマートフォンの普及、SNSによる顧客接点の変化が、メーカーと顧客の直接的な結びつきを可能にしました。
この「Direct to Consumer(D2C)」モデルでは、メーカーがECサイトで商品を販売し、SNSを通じてブランディングとファン育成を行います。
ShopifyやBASEといったノーコードツールの登場により、技術力がなくても誰でも簡単に自社ECを持てるようになりました。
中川政七商店のように、直営店舗とECを併用してブランドを構築したSPA型モデルは、D2Cの日本型成功例として高く評価されています。
2. メーカー直販が変える収益モデルと商品戦略
D2Cの最大のメリットは、中間マージンをカットして利益率を向上できる点です。従来は卸業者や小売業者の方々に多くの利益が取られていましたが、D2Cでは、その分を製品改良・顧客体験の向上に充てることができます。
例えば、完全栄養食「BASE FOOD」は、ECと定期購入モデルを組み合わせ、広告とSNSで顧客との関係を構築します。広告費はかかるものの、商品企画から販売、ブランディングまですべて自社完結で行い、顧客ロイヤルティを高めることに成功しました。
また、アメリカ発の「Warby Parker」は、メガネをECで注文できるD2Cモデルで話題になりました。自宅試着サービスやAR試着機能により、体験価値を提供してリアル店舗を持たずにブランド価値を構築。結果として大手小売を介さずグローバル展開を実現しています。
このように、メーカーが「誰に、どんな体験を、どのチャネルで提供するか」を戦略的に設計できるようになったのが、現代D2Cの本質です。
3. 変容する“中間”業者の新しい役割
「中抜き」がなくなる一方で、新しい“つなぎ手”としての中間業者の存在が注目されています。それは旧来の問屋や小売ではなく、テクノロジーやサービスで支援する企業です。
3.1 プラットフォーム型支援
例えば、ShopifyやBASEは、自社ECサイトを構築・運用するインフラとして機能し、決済や在庫管理、分析までを簡単に提供しています。これにより、企業は開発や運営のコストを抑えながら、独自ブランドを持つことが可能になります。
また、越境EC支援の「Buyee Connect」は、海外への販売時に必要な翻訳や決済、物流、カスタマーサポートを一括で代行できます。これにより、英語や中国語ができなくても海外進出できる環境が整いつつあります。
3.2 マーケティングやCXの支援業者
インフルエンサーとのマッチングを行うTagpicや、ライブコマース支援のLiveParkなども、D2Cのスピーディーな顧客接点構築において欠かせません。つまり、「中間業者=不要」ではなく、価値を再編集・支援する中間者が新たに生まれていると捉えるべきでしょう。
4. 成功事例から学ぶD2C実践モデル
ここでは、国内外で成功しているD2Cブランドを3つご紹介します。ぜひ、参考にしてみてください。
中川政七商店(日本)
中川政七商店は、奈良の老舗メーカーが直営店+ECでSPA業態を構築しており、伝統工芸を“ライフスタイル提案型ブランド”に進化させ、地方企業のロールモデルとなりました。
SOÉJU(日本)
SOÉJUは、プロスタイルを取り入れたアパレルD2Cです。AR試着やチャット相談を駆使し、「試着できない不安」をテクノロジーで解消します。また、予約販売・AIレコメンドも導入しています。
Allbirds(アメリカ)
Allbirdsは、アメリカのエコ素材のシューズブランドです。D2C+サステナビリティの文脈で話題化し、SNSとパーパスブランディングを掛け合わせてロイヤルカスタマーを獲得しています。
5. 業者別の今後のアクションガイド
ここでは、今後どのようなことに気をつけて行動するべきか、業者別にわけて簡潔に説明いたします。ぜひ、ご参考になさってください。
製造業の方向け
技術力はあるが販路に悩んでいるなら、ShopifyやBASEを活用して小ロットでも試験販売を。顧客の声を聞ける場を持つことが第一歩です。
小売業の方向け
独自商品があるなら、自社ブランド化して直販に挑戦することをおすすめします。D2C支援パートナーと組むことで、人的リソースの不安も解消可能です。
マーケター・広報担当の方向け
“モノを売る”ではなく、“顧客体験を設計する”という視点が重要になります。D2Cは施策のPDCAを高速で回す実験場にもなるでしょう。
まとめ
中抜き構造の崩壊は、単なる構造の変化ではなく、価値の再定義と顧客接点の主導権を取り戻す動きです。メーカーがD2Cによって顧客と直接つながることで、製品開発・価格・世界観のすべてを自ら設計できるようになりました。
これは、中小企業や地域ブランド、職人ビジネスにも大きな機会をもたらします。そして、新たな中間支援者の登場により、「直販=孤独」という時代は終わりました。ビジネスのあり方は、信頼と体験を中心にした経済構造へと確実に動いています。
今後の市場では、D2Cが単なる販路ではなく、「顧客との関係性をどう築くか」の戦略軸としてより重視されるでしょう。小さなブランドほど機動力を活かしやすく、デジタルの力を借りて“選ばれる理由”を発信できれば、大手とも戦える時代です。
あなたのビジネスにも、直販戦略の視点を加えることで次の成長フェーズが見えてくるでしょう。
参考文献
経済産業省「令和5年度中堅・中小企業輸出ビジネスモデル調査・実証事業」報告書(PDF)
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2023FY/000225.pdf
Forbes JAPAN「D2Cは下火になったのか?『D2C 3.0』マーケティング戦略とは」
https://forbesjapan.com/articles/detail/51927
Shopify日本公式ブログ「D2Cとは?導入のメリット・デメリットや成功事例」
https://www.shopify.jp/blog/d2c-ecommerce
井上達彦研究室「希少品のSPA業態を可能にするバリューチェーン構築 ~ビジネスモデル分析紹介 中川政七商店編~」
https://note.com/inouelabo/n/n0ce48371e377
弘前大学学術情報リポジトリ「中川政七商店のブランディング戦略」
https://hirosaki.repo.nii.ac.jp/record/6691/files/RegionalStudies_18_3.pdf