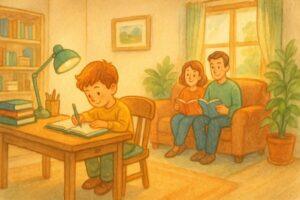医療費がかさんだ年、「少しでも税金を取り戻したい」と考える方は多いのではないでしょうか。その代表的な制度が「医療費控除」です。毎年の確定申告シーズンになると話題にのぼるこの制度ですが、実は正しく理解して活用しなければ、思わぬ落とし穴にはまる可能性もあります。
たとえば、「保険金が出たら控除がゼロになる?」、「交通費はどこまで含められる?」、「ふるさと納税をしているとワンストップ特例が使えなくなる?」など、制度の仕組みを誤解して損をしてしまうケースも少なくありません。
本記事では、医療費控除の基本的な仕組みから、節税につなげるポイント、そして見落としがちな「知られざる落とし穴」までを、分かりやすく解説していきます。正しい知識を持って、確定申告を有利に進めていきましょう。

1. 医療費控除の基本と対象の仕組み</h2>
1-1. 医療費控除の概要と計算式</h3>
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税の一部が還付される制度です。年間の医療費合計から「10万円」または「総所得の5%」のいずれか少ない金額を差し引いた金額が、控除対象となります(上限200万円)。
たとえば、総所得が300万円の人が15万円の医療費を支払った場合、控除対象額は15万円−(300万円×5%)=0円。一方、同じ15万円でも総所得が500万円の人は15万円−10万円=5万円が控除対象になります。課税所得を圧縮できれば、結果として税額も軽減されます。
1-2. 控除対象になる医療費の範囲
控除の対象になるのは、治療や診療にかかった費用です。診察代、入院費、処方薬代のほか、妊娠・出産費用、通院時の公共交通機関の交通費、条件を満たす介護費用も含まれます。
ただし、美容整形やホワイトニング、健康診断など、治療目的でないものは原則として対象外です。また、セルフメディケーション税制との併用はできませんので、どちらが得か比較して選びましょう。
1-3. 家族分も合算して申告できる
医療費控除では、生計を一にする家族の分も合算できます。たとえば、子どもや高齢の親の医療費も含めて申告できるため、合計額が大きくなりやすく、控除額を増やせる可能性があります。
共働きの場合は、所得が多い方が申請したほうが節税効果が高まる傾向があります。事前にシミュレーションを行い、どちらが有利か確認しておくと安心です。
2. 控除を使えば節税になる理由とは
2-1. 控除が節約につながる仕組み
医療費控除は「課税所得」を減らす効果があります。課税所得が下がれば、結果として所得税・住民税も軽減され、還付金として返ってくる可能性があります。
たとえば10万円分の医療費控除が受けられると、所得税率が10%の人であれば1万円の税金が軽減されることになります。実際の還付額は人によって異なりますが、「申告しなければゼロ」なので、忘れずに確認しましょう。
2-2. 低所得でも活用できる制度
総所得が200万円未満の場合、基準額は10万円ではなく「所得の5%」となるため、比較的少額の医療費でも控除対象になります。年金生活者やパート主婦でも、十分に活用できる制度です。
加えて、医療費控除は所得税の還付だけでなく、翌年の住民税軽減にもつながります。税の二重メリットがある点も、見逃せないポイントでしょう。
3. 見落としがちな制度の落とし穴
3-1. 保険金の補填で控除額ゼロに?
医療保険や共済から給付金が出た場合、医療費からその金額を差し引く必要があります。たとえば20万円の治療費に対して10万円の保険金を受け取った場合、控除対象となるのは残りの10万円です。
この計算を知らずに申告すると、「控除対象のつもりがゼロだった」ということもあり得ます。保険や共済の給付内容はしっかり確認しましょう。
3-2. ふるさと納税と確定申告の関係
ふるさと納税をワンストップ特例で済ませていた場合でも、医療費控除を申請するために確定申告を行うと、その特例は無効になります。つまり、ふるさと納税分も改めて確定申告が必要です。
特例のつもりで手続きを省略してしまうと、翌年になって「住民税が減っていない」という事態もあります。医療費控除とセットで、ふるさと納税の申告内容も見直しましょう。
3-3. 通院交通費や家族分を申告し忘れる
公共交通機関による通院交通費は控除対象です。たとえばバスや電車での通院にかかった運賃は、レシートがなくても記録しておけば申告できます(タクシーは原則NG)。
また、本人だけでなく家族の医療費も合算できる点は見落としがちです。自分の医療費が少なくても、子どもや親の通院費を含めると基準額を超える場合もあります。1年分の医療費を一覧で整理し、申告漏れを防ぎましょう。
4. 上手に申告するための準備とコツ
4-1. 明細書と領収証の管理はこまめに
申告には「医療費控除の明細書」が必要です。支払先、日付、金額、対象者などを正確に記載する必要があります。2023年からは領収証の提出は不要になりましたが、5年間の保管義務があるため、破棄しないよう注意しましょう。
こまめにエクセルやノートに記録を残し、月ごとに分類しておけば申告時の手間が省けます。クラウド会計ソフトや無料アプリも活用すれば、初めての人でもスムーズに作業できます。
4-2. e-Taxを活用してスピーディーに申告
オンライン申告ができる「e-Tax」は、税務署に行かずに申告ができる便利な方法です。マイナンバーカードとスマートフォン、もしくはICカードリーダーがあれば、家からでも申告が完了します。
e-Taxには自動計算や控除チェック機能もあるため、誤入力を防ぎながら効率よく手続きを進められます。還付金の振込も早くなる傾向があるため、時間も手間も節約できます。
5. まとめ
医療費控除は、医療費がかさんだ年の家計を支える心強い制度です。しかし、対象費用や控除額の計算方法、他制度との関係を正しく理解しないと、本来得られるはずの還付金を逃してしまうことにもなりかねません。制度の仕組みや注意点をしっかりと把握し、事前に準備を整えることで、無理なく節税につなげることができます。控除を活用するかどうかで、税負担には意外な差が生まれるものです。まずは、領収証の整理から始めてみましょう。
参考文献
ダイヤモンド・オンライン|「医療費控除で『知らないと大損』する意外な落とし穴!」 https://diamond.jp/articles/-/359217
マネーポストWEB|「確定申告『医療費控除』の落とし穴 ふるさと納税のワンストップ…」 https://www.moneypost.jp/990461
サライ.jp|「医療費がかさんだら確定申告で税金を取り戻す節約技」 https://serai.jp/living/1231922
note/菅安翔氏|「医療費控除のしくみと落とし穴 確定申告で損しないために知って…」 https://note.com/shun_ando/n/n1f447bfa07e0
freee|「10万円ちょっとの医療費で控除を受けるのは意味ない?」 https://www.freee.co.jp/kb/kb-blue-return/blue-return-medical/
創業手帳|「医療費控除の対象になる費用は?節税につながるポイント」 https://sogyotecho.jp/iryouhikoujyo-taishou/
税理士法人淀川パートナーズ|「医療費控除とは?概要や節税のポイントについて解説!」 https://yodogawa-partners.or.jp/blog/medicalcredit/