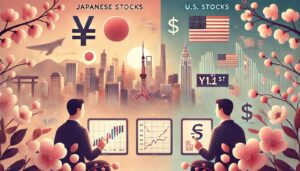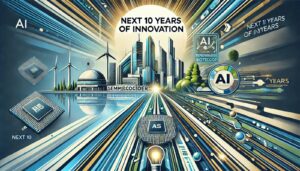近年、物価上昇と円安の影響を受け、日本国内にとどまらず海外不動産に目を向ける投資家が急増しています。2025年現在、世界各地で不動産価格の調整が進みつつも、国によっては金利の低下や需要回復の兆しが見られ、買い時とされるエリアが複数存在しています。
本記事では、「今、海外不動産を買うべきか?」という問いに対し、アジアとヨーロッパの注目都市を比較しながら、利回りや投資リスク、将来性を明確に整理します。

1.なぜ今、海外不動産が注目されるのか
2025年の海外不動産投資市場は、「インフレ対策」「金利変動」「為替分散」など、複合的な資産戦略の一環として、個人・法人を問わず多くの投資家が関心を寄せる分野です。その背景には、次のような要因があります。
1-1.世界的なインフレと通貨の分散需要
近年、欧米を中心に続いた量的緩和の副作用として、先進国を含む多くの地域でインフレ率が高止まりしています。こうした中で「現金」や「国債」ではなく、「実物資産」である不動産が再評価されています。
特に海外不動産は、円だけでなく米ドル、ユーロ、豪ドル、ASEAN通貨など、通貨分散が可能な手段として注目され、資産のインフレ耐性を高める効果があります。たとえば、米国不動産からドル建ての家賃収入を得ることで、為替リスクを収益源に転化する投資家も増加しています。
1-2.金利環境の変化と融資のタイミング
オーストラリアやカナダなど、一部の国では2025年に入ってから政策金利が引き下げに転じました。これにより、住宅ローンの借入金利が低下し、現地で融資を受ける外国人投資家にも恩恵が及んでいます。中でも、オーストラリアでは自国民・外国人問わず、融資競争が再燃しつつあり、投資活動の再加速が予測されています。
一方、ベトナムやタイなどの新興国では、まだローン取得のハードルが高く、基本的にはキャッシュ投資が主流です。ただし、価格水準が日本と比べて割安なため、初期費用が抑えられるというメリットがあります。
1-3.コロナ後の都市構造変化とエンドユーザー需要の高まり
パンデミックを機に都市と人の関係が見直され、リモートワークやセカンドホームへの関心が高まりました。こうした動きは、従来の「キャピタルゲイン狙い」だけでなく、自己利用も可能な物件を前提とした投資ニーズを生んでいます。
たとえば、ドバイやリスボンでは、高所得層の移住者やノマドワーカーの流入により、居住用不動産の価格が上昇傾向にあります。これらは中長期的な実需に裏打ちされた投資市場であり、「空室になりにくい=利回りが安定する」という評価軸でも有望とされています。
2.アジアの成長都市と利回り比較
2-1.ベトナム|政策緩和と都市化で注目
ホーチミンやハノイでは、表面利回りは約4%とされており、東南アジアの中でも安定感のある水準です。特に2015年の法改正以降、外国人によるコンドミニアム所有が解禁されたことで、外資が本格的に流入しました。
ただし、中古物件の流通には制限があり、原則として外国人が所有できる割合にも上限があります。法人名義での賃貸運用には追加の条件が課されるケースもあるため、現地の法律に精通した専門家のサポートが不可欠です。
また、ホーチミンでは価格が調整局面に入りつつあるため、今後のキャピタルゲインを狙うには、プロジェクトごとの選別と見極めが重要になるでしょう。
2-2.フィリピン|キャピタルとインカムの両方が狙える市場
マニラでは、経済成長に伴い住宅価格が上昇を続けており、年5〜6%の利回りが期待できる投資先です。人口構成は非常に若く、住宅取得層が拡大していることに加え、OFW(海外労働者)からの送金による経済の安定性も特徴的です。
外国人は土地を所有できないため、投資対象はコンドミニアムに限られますが、物件数は豊富で価格帯も幅広く、1,000万円前後から購入可能なプロジェクトもあります。多くの日系企業が不動産開発に参入しており、賃貸管理体制も充実しています。
2-3.マレーシア|MM2Hと安定的利回り
クアラルンプールやジョホールバルといった主要都市では、表面利回りは4.5%前後と堅調です。特に、長期滞在が可能なMM2H(マレーシア・マイ・セカンド・ホーム)ビザ制度は、日本人にとって移住と投資の両面で魅力的な選択肢となっています。英語が広く通じ、インフラも整っているため、外国人の生活適応コストが低く済む点も安心材料の一つです。海外不動産投資の初心者でも比較的始めやすい国といえます。
2-4.タイ|成熟市場と新興エリアの二極化
バンコク中心部の不動産市場はすでに成熟しており、利回りは4〜5%で安定しています。ただし価格の上昇は落ち着いてきており、今後は郊外エリアに注目が集まる見込みです。
特にバンナーやラップラオといった新興エリアでは、新たな鉄道網の整備やショッピングモールの建設が進み、資産価値の向上が見込まれています。
タイでは外国人の土地所有は認められていませんが、コンドミニアムについては比較的柔軟な制度が整っており、個人投資家にとって参入しやすい環境といえます。
3.ヨーロッパの注目国と投資の安定性
3-1.ポルトガル|ゴールデンビザ終了後も根強い人気
ポルトガルでは2023年にゴールデンビザ制度が改正され、都市部の不動産による取得条件が大幅に厳格化されました。しかし、地方都市や郊外では魅力的なプロジェクトが依然として多く、観光需要の高さから短期賃貸の収益性は高水準を維持しています。
特にポルトやカスカイスでは、短期賃貸用物件の表面利回りが5〜8%と高く、住宅不足も背景に稼働率も良好です。ただし、自治体ごとにライセンス取得条件が異なるため、法的手続きの確認は必須です。
3-2.アイルランド|IT企業集積による堅実な成長
ダブリンは欧州のITハブとして急成長しており、GoogleやMetaといったグローバル企業の欧州本社が集まっています。これにより都市部での住宅需要が高まり、利回りも約7%と欧州内では異例の水準にあります。
EU域内で英語が通じる数少ない国であり、法人税率の低さから今後も外資誘致が進むと見られています。ただし、初期費用は高額で、物件価格が60万ユーロを超えるものも多いため、ローン活用や購入スキームの検討が必要です。
3-3.ドイツ|安定性と所有権保護で根強い人気
ベルリンやミュンヘンといった大都市では、賃貸需要が旺盛で、物件の供給不足が続いています。ドイツの不動産市場の特徴は、所有権保護と法制度の透明性の高さにあります。登記制度も非常に厳格で、外国人でも安心して物件を保有できます。
表面利回りは3〜5%と控えめですが、安定した賃料と高い入居率により、インカムゲインが安定しています。価格の急上昇は期待しにくいものの、リスクヘッジ目的の長期保有には適した市場といえるでしょう。
4.まとめ
2025年の海外不動産市場は、アジア・ヨーロッパともに投資家の目的や戦略によって選択肢は大きく分かれます。高利回りを狙うのであれば、フィリピンやベトナムなどの成長市場が有力で、安定した資産形成を重視する場合には、ドイツやアイルランドが堅実な選択肢となります。
為替や金利のタイミング、現地の法制度を正しく把握し、自身のポートフォリオに合った地域を選定することが、海外不動産投資の成功に向けた第一歩となります。
5.参考文献
- 藤和ハウス「2025年に狙うべき海外不動産投資先ランキング」
https://kaigai.fujic21.com/post/614/ - 藤和ハウス「2025年の海外不動産市場はどうなる?最新予測と注目エリア」
https://kaigai.fujic21.com/post/723/ - ライフグループ「アジアvsヨーロッパ、海外不動産投資の徹底比較」
https://note.com/lifegroup/n/nfacdedc586b8 - セカイプロパティ「【2025年最新】海外不動産投資の国別利回りランキング!」
https://ja.sekaiproperty.com/article/2833/oversea-property-yield - KlearPictureGlobal「オーストラリア不動産市場は次の上昇局面へ」
https://note.com/klear_picture/n/na54c18f96cd5 - PGIM「グローバル不動産市場見通し2025年版」
https://www.pgim.com/jp/ja/insights/pgim-real-estate-global-outlook-2025