配偶者控除と育児休業給付金は、どちらも子育て世代には身近な制度ですが、「何が違うのか」「どちらにどんなメリットがあるのか」を正しく説明できる方は意外と少ないかもしれません。特に育休中の所得や扶養、税金との関係は、制度が複雑に絡み合っていて混乱しがちです。
たとえば、「育児休業給付金をもらっていても配偶者控除は受けられるの?」「夫の扶養に入れるかどうかはどこで判断するの?」といった疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。
この記事では、育児中に気になる「配偶者控除」と「育児休業給付金」の制度を、最新の情報とともにわかりやすく解説します。それぞれの仕組みや適用条件、具体的な違いを把握することで、制度を上手に活用し、家計の負担を減らすヒントを得られるでしょう。
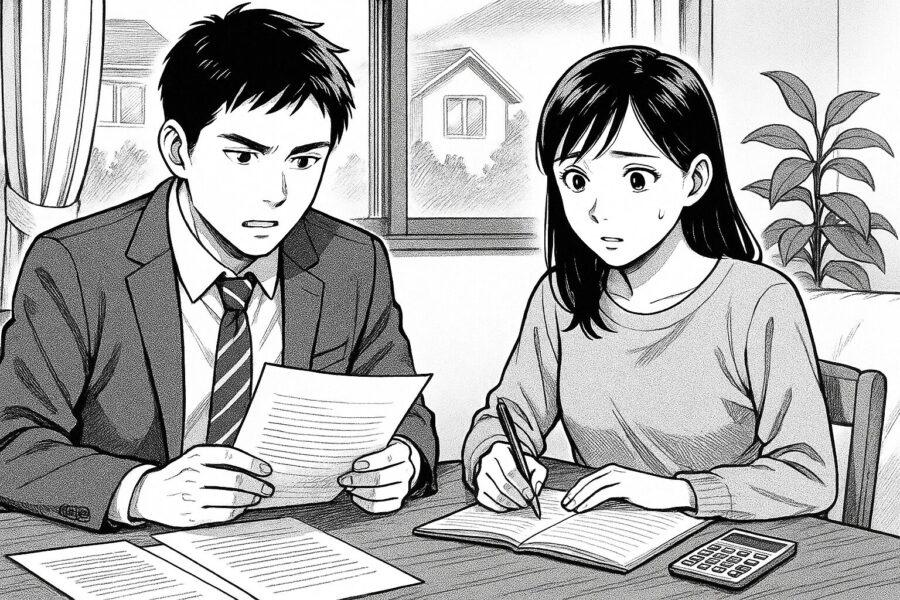
1. 配偶者控除とは何かを理解しよう
配偶者控除とは、納税者の配偶者に一定の所得制限がある場合に、税負担を軽減するための制度です。主に所得税と住民税の計算時に利用され、家計全体の節税につながります。適用にはいくつかの条件があり、控除を受ける本人が納税義務者であること、配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみなら年収103万円以下)であることが必要です。さらに、本人の所得が900万円(年収でおよそ1,120万円)を超えると対象外になります。配偶者の所得がそれ以上ある場合は、「配偶者特別控除」の対象となり、所得に応じて控除額が段階的に減額されます。また、配偶者控除の適用において判断されるのは課税対象の所得であり、育児休業給付金や出産手当金などの非課税所得は含まれません。そのため、これらの給付金を受け取っていても控除への影響はなく、正確な理解が必要です。
2. 育児休業給付金の仕組みと条件
育児休業給付金は、雇用保険に加入している人が育児のために休業した場合に受け取れる支援金です。出産後の「出産手当金」期間が終わったあと、育児休業に入ることで支給が始まります。受給には、育休開始前の2年間で11日以上働いた月が12か月以上あることが条件です。支給額は休業前の賃金の67%(最初の180日間)、その後は50%に下がりますが、一定の上限があります。注目すべきは、この給付金が「非課税所得」とされる点です。
つまり、所得税や住民税はかかりません。この非課税扱いにより、配偶者控除の対象になるかどうかの判断には影響しないのです。たとえ月15万円の給付金を受け取っていても、それは「所得」とはみなされず、税制上の控除に不利になることはありません。この仕組みを正しく理解しておくことが大切です。
3. 控除と給付金の違いと関係性
3-1 配偶者控除と育児休業給付金の違いとは
配偶者控除と育児休業給付金は、どちらも育児中の家庭を支援する制度ですが、その目的や仕組みには大きな違いがあります。配偶者控除は所得税や住民税を軽減するための「税制上の優遇措置」であり、一定の条件を満たす配偶者がいる場合に、納税者の課税所得を減らす効果があります。
一方、育児休業給付金は雇用保険制度によって支給されるもので、育児のために仕事を休んでいる間の生活費を補う「所得保障」の役割を果たします。つまり、配偶者控除は税金を減らす制度、育児休業給付金は収入の代わりになる支給金という位置づけです。これらは併用できるものであり、どちらか一方を選ばなければならないという関係ではありません。
3-2 育児休業給付金は非課税、控除の対象にも影響なし
続いて重要なのは、育児休業給付金が非課税であるという点です。このため、育休中に給付金を受け取っていたとしても、それが課税所得に含まれない限り、配偶者控除や配偶者特別控除の判定に影響を与えません。たとえば、育休中の配偶者が給付金のみで他に収入がない場合、課税所得が48万円以下とみなされ、配偶者控除の対象になることがあります。
また、令和7年からは配偶者特別控除の適用上限が引き上げられ、年収123万円までが対象となる予定です。これにより、短時間のパートなどで収入がある場合でも控除を受けられる可能性が広がります。
3-3 控除の適用には収入の合計と働き方がカギ
実際に控除が適用されるかどうかは、給付金以外の収入や働き方によって変わってきます。たとえば、育休中に在宅ワークで年間50万円の所得があると、48万円の上限を超えるため配偶者控除は適用されませんが、配偶者特別控除の対象にはなり得ます。
逆に、年間150万円のパート収入があると、どちらの控除にも該当しない可能性があります。このように、税制上の控除と社会保障給付金はそれぞれ独立した制度でありつつも、家庭の収入状況に応じて柔軟に活用することができます。制度の正しい理解と、タイミングを見た働き方の選択が、家計を安定させる大きな鍵となります。
4. よくある勘違いと注意ポイント
育児休業給付金に関して、「収入」と誤解してしまう人が多く見られますが、実際には課税対象外であり、配偶者控除の判定には含まれません。この誤認により控除を諦めてしまうのは非常にもったいないことです。
また、扶養の基準は税制と社会保険で異なるため注意が必要です。税制上は所得48万円以下が基準ですが、健康保険では一般的に年収130万円未満が目安とされています。そのため、税制上では控除対象でも、保険では扶養に入れないケースがあります。
さらに、育休中に配偶者控除を受けるには、年末調整や確定申告で正確な申告が必要です。給付金を誤って収入に含めると控除が受けられない可能性もあります。その他、在宅ワークやフリマアプリでの収入も所得に含まれる場合があるため、きちんと把握し、申告内容を整理しておくことが重要です。
5. まとめ
配偶者控除と育児休業給付金は、それぞれ異なる制度ですが、子育て家庭の経済的支援として併用できる重要な制度です。育児休業給付金は非課税であり、配偶者控除の判定には含まれません。したがって、条件さえ満たせば両制度を併用し、節税しながら家計の安定を図ることが可能です。制度の違いと関係性を正しく理解し、年末調整や確定申告で漏れのない手続きを行うことが、家計の負担を軽減する第一歩となります。
参考文献
– 育休中に扶養に入るとどうなる?控除額や手続きの流れを解説|MoneyForward
– 産休・育休中も配偶者(特別)控除を活用して節税しよう|楽天カード
– No.1191 配偶者控除|国税庁
– 育休中に配偶者控除は適用される?|SBIマネープラザ https://mponline.sbi-moneyplaza.co.jp/money/education/20211115ikukyu-haigushakoujyo.html
– 育休中も扶養に入れる?控除額や手続き|LITALICO発達ナビ
– 【令和7年版】出産手当金や育児休業給付金があると配偶者控除は…|ShokonoAruIe
– 育休中に夫の扶養に入るデメリット・手当|Money-Career





