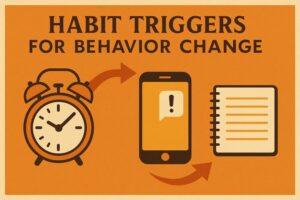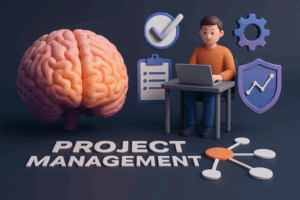起業を目指す人にとって、ビジネスプランや商品開発と並んで重要なのが「資金調達」です。その中でも、金融機関などからお金を借りる「融資」は、多くの起業家が頼る手段のひとつです。しかし、融資にあたって最も見落とされがちなのが「金利」の理解です。
金利は単なる数値ではなく、借入額・返済期間・事業の健全性に直結する重要な要素です。金利を甘く見ると、当初の想定よりも返済総額が大幅に膨らみ、キャッシュフローに深刻な影響を及ぼすリスクもあります。
この記事では、起業を考える段階で知っておくべき「金利」と「借入」の基礎知識を、わかりやすく解説していきます。金融機関や公的支援制度の特徴、金利を低く抑えるコツまで網羅的に取り上げるので、これから起業を目指す方はぜひ最後までご覧ください。

1. 起業時に知るべき借入の基本
起業には多くの資金が必要であり、設備投資や人件費、日々の運転資金など、初期段階での出費は大きな負担となります。こうしたコストをすべて自己資金だけでまかなうのは難しいのが現実です。
そこで、多くの起業家が利用するのが「事業用融資」です。融資とは、金融機関や公的機関から利息を支払うことを前提に資金を借り入れることであり、起業家にとっては事業の立ち上げや成長を支える重要な手段となります。
ただし、借りた資金を健全に活用し、計画的に返済できる力が求められます。特に起業初期には「創業融資」や「制度融資」といった支援制度が用意されており、日本政策金融公庫などが代表的な貸し手となります。
これらは無担保・無保証でも利用できる場合があり、金利も比較的低く設定されているのが特徴です。融資の種類には、政策金融機関からの低金利のもの、信用力によって金利が大きく変わる民間金融機関のビジネスローン、そして審査が早い一方で金利が高めなノンバンク系などがあります。
返済方式にも種類があり、「元利均等返済」は毎月の支払額が一定で計画が立てやすく、「元金均等返済」は総返済額を抑えられる傾向があります。それぞれの特徴を理解し、自社の状況に応じて選ぶことが重要です。
また、金融機関は自己資金の比率も重視しており、総資金のうち30%以上が自己資金であると、融資審査で好印象を与えるとされています。起業を成功させるためには、準備段階からの資金形成がカギとなるでしょう。
2. 金利の種類と計算方法を理解
金利にはいくつかの種類があり、それぞれの特徴を理解することは、起業時の資金計画において非常に重要です。もし金利の仕組みを正しく理解していなければ、将来的に返済が困難となるリスクを抱えることになります。
特に代表的な金利の形態として「固定金利」と「変動金利」があります。
固定金利は、契約時に決められた金利が返済期間中ずっと変わらない方式であり、返済額の見通しが立てやすく、資金計画も安定しやすいという利点があります。ただし、市場金利が下落したとしても金利は下がらないため、結果的に割高になる可能性があります。
反対に変動金利は、市場の動きに応じて金利が見直される仕組みであり、市場金利が下がれば返済額も軽減されるメリットがありますが、逆に金利が上昇すれば返済負担が増すリスクも伴います。
加えて、利息の計算方法を理解しておくことも大切です。利息は基本的に元金に金利を掛けて算出されます。例えば300万円を年利2%で借りて5年で返済する場合、元利均等方式では利息総額は約15万円、月々の返済額はおよそ5万2,500円程度になります。さらに、表面金利と実質金利の違いにも注意が必要です。表面金利はあくまで契約書上の数値であり、保証料や手数料を含まないため、実際の返済額とは一致しないことがあります。
実質金利はこれらの諸費用を含めた実際の借入コストを示すもので、より現実的な資金計画を立てるうえで参考になるでしょう。
3. 融資先ごとの特徴と金利相場
起業時に利用できる融資には、公的機関と民間機関の二つの選択肢があります。それぞれの融資先には金利や条件に違いがあるため、自分の事業計画や返済能力に応じて最適なものを選ぶことが、起業を成功させるうえでの第一歩になります。
たとえば、日本政策金融公庫では、創業者向けに1%〜3%程度の低金利で融資が可能で、担保や保証人が不要な「新創業融資制度」なども用意されています。審査基準も比較的柔軟で、初めての起業でも利用しやすいのが特徴です。
また、東京都をはじめとする地方自治体でも、起業支援を目的とした制度融資が整っており、「外国人起業家支援プログラム」などでは最大2.7%以下の固定金利で借入れができます。民間の融資では、地方銀行や信用金庫が一般的で、担保や保証人が必要になることが多いですが、信用力や取引実績が評価されやすく、金利は1.9〜7.8%の範囲で設定されることがあります。
さらに、ノンバンクと呼ばれる消費者金融やビジネスローン専門業者も利用可能ですが、こちらは審査が早く即時融資が可能な反面、金利が3〜18%と高めに設定されています。したがって、ノンバンクを利用する場合は、短期返済を前提にして借り過ぎを防ぎ、返済計画をしっかり立てることが欠かせません。
4. 金利を抑えるための実践対策
起業時に融資を受ける際は、わずかな金利差が長期的に見て大きな返済負担の差につながることがあります。そのため、金利を少しでも低く抑えるためには、事前の準備と十分な情報収集が欠かせません。
たとえば、返済期間を7年以内に設定することで、金利が優遇されるケースがあります。また、担保や保証人を用意することで信用力が高まり、金融機関が安心して融資しやすくなります。
さらに、売上予測や市場分析を盛り込んだ具体的な事業計画書を提出すれば、審査時の印象が良くなり、条件の良い融資を引き出せる可能性が高まります。そのほか、公庫の融資と銀行の制度融資など、複数の制度を比較検討し、自身にとって最も有利な条件を見極める姿勢も非常に重要です。
5. まとめ
起業を成功させるには、アイデアや商品力だけでなく、資金の扱い方も非常に重要です。特に「金利」の知識を持たずに借入を行うと、返済に追われ経営が立ち行かなくなるリスクもあります。金利の仕組み、融資先の特徴、金利を抑える工夫をしっかり理解し、資金調達を戦略的に進めることが、起業を成功に導くカギとなるでしょう。
参考文献
- 日本政策金融公庫「創業融資のご案内」
jfc.go.jp。 - 日本政策金融公庫「国民生活事業および中小企業事業の主要利率一覧表」
sogyotecho.jp+2jfc.go.jp+2jfc.go.jp+2。 - Japan‑Finance.jp「日本政策金融公庫の創業融資の金利は1.0%~3.0%」
jfc.go.jp+9japan-finance.jp+9oyama-toshiro.com+9。 - 創業手帳「日本政策金融公庫の融資を受けたい!事前に知っておきたい金利を…」
sogyotecho.jp+1jfc.go.jp+1。 - Newity Market「Fixed vs Variable Interest Loans: Which is Better for Your Business?」
bankrate.com+11newitymarket.com+11nextinsurance.com+