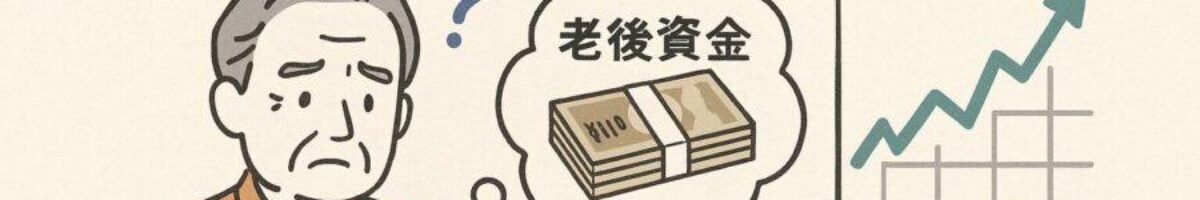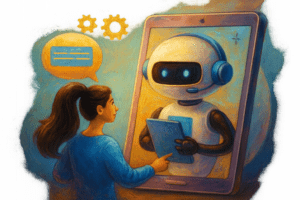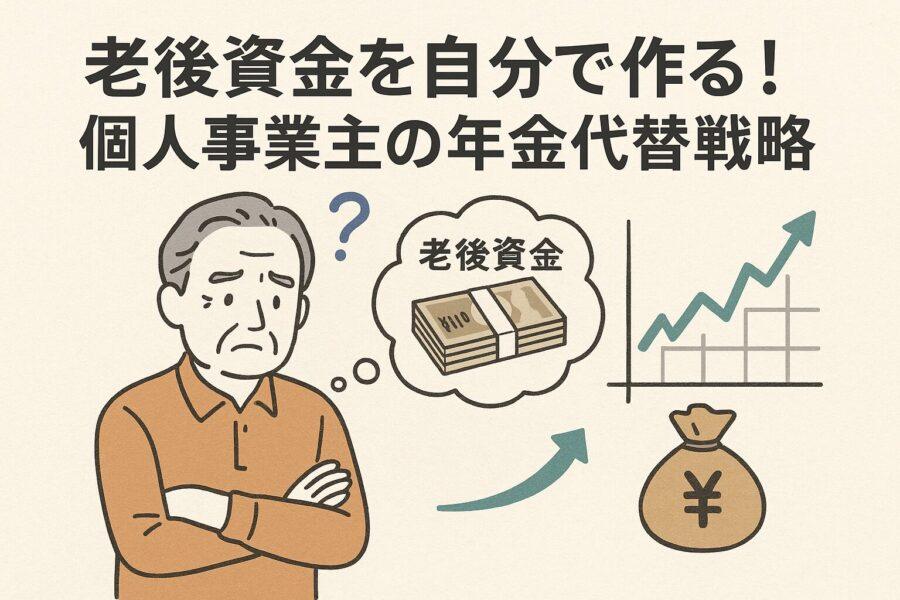
「老後2,000万円問題」と呼ばれる社会課題が浮き彫りになって久しい今、特に国民年金のみの個人事業主にとっては切実な問題です。会社員のように厚生年金に加入できない自営業者は、自力で老後資金を準備する必要があります。そこで本記事では、年金に代わる制度や投資を通じて、老後資金を形成するための実践的な戦略をご紹介します。老後に不安を残さないためにも、今日からできる第一歩を一緒に学んでいきましょう。
1. なぜ国民年金だけでは老後資金が足りないのか?
日本の公的年金制度は、基礎年金(国民年金)と厚生年金からなる2階建て構造です。会社員はこの両方に加入していますが、個人事業主は原則として基礎年金のみ。2025年現在、満額の国民年金を受給しても月額は約6万6,000円にとどまります。
この金額では家賃や光熱費、食費を含めた基本的な生活費をまかなうことすら難しく、年金だけでは老後の安心は得られません。
さらに、金融庁の2019年報告書では、夫婦2人の老後生活において約2,000万円の資金不足が生じると推定されています。これは厚生年金のある前提での試算です。つまり、個人事業主にとっては、さらに多くの資金準備が必要となります。
加えて、国民年金は65歳から支給されるため、それまでの期間をどう生活するかという視点も重要です。仮に60歳で引退しても、年金を受け取れるまでの5年間を自力で支える必要があるため、短期的な生活費の備えも忘れてはいけません。
また、2022年の総務省「家計調査」によれば、高齢夫婦無職世帯の月平均支出は約23万6,000円でした。これに対し、年金収入の平均は約20万円。毎月約3万円以上の赤字が発生しているのが現実であり、貯蓄や投資による補填が不可欠なのです。
2. 年金代替となる制度と投資戦略の正しい選び方
老後資金を自分で用意するためには、税制優遇を受けられる制度や、長期投資による資産形成が重要なカギとなります。ここでは代表的な制度と投資商品を紹介し、それぞれの特徴を解説します。
まず、小規模企業共済は中小機構が運営する制度で、個人事業主向けの“退職金制度”とも言われています。月額1,000円から7万円まで掛金を設定でき、全額が所得控除の対象となるのが大きな特徴です。長期的に積み立てることで、税制優遇を受けつつ退職金のような形で資金を受け取ることができます。
次に紹介するiDeCo(個人型確定拠出年金)は、自分で投資運用しながら老後資金を形成できる制度です。毎月5,000円から積立が可能で、掛金は全額所得控除、さらに運用益は非課税となります。受取時にも退職所得控除や公的年金控除が適用されるため、税の三重優遇を受けられる点が魅力です。
また、新NISA(2024年制度改正後)は年間最大360万円までの投資が非課税対象となり、つみたて枠と成長投資枠の両方を使うことができます。iDeCoと違って途中で資金を引き出せるため、流動性を確保したい個人事業主には使いやすい制度です。
なお、iDeCoには注意点もあります。たとえば60歳まで引き出せないという制約や、毎月の掛金に上限があること、また商品選びによっては元本割れのリスクがあることなどです。そのため、NISAなどとの併用でリスク分散を図ることが現実的な戦略となるでしょう。
3. 投資初心者でも始めやすい老後資産の運用方法とは?
老後資金を増やすためには、ただ貯金するのではなく、「資産を増やす工夫」が必要です。特に長期間にわたる投資は、複利の力を活かすことで元本を大きく育てる可能性を秘めています。
例えば、毎月3万円を年利4%で30年間運用した場合、元本1,080万円に対して運用益は約1,150万円、合計で2,200万円を超える資産が形成される計算になります。このように、時間を味方につける長期投資は非常に効果的です。
初心者には、投資信託を利用した「つみたて投資」が便利です。毎月一定額を同じ商品に積み立てることで、価格変動の影響を平均化できる「ドルコスト平均法」が働き、心理的負担も軽減されます。
投資先としては、低コストで世界中に分散投資ができる「インデックスファンド」が人気です。楽天・全世界株式インデックス・ファンドや、eMAXIS Slimシリーズ(全世界株式、S&P500など)は、多くの証券会社で取り扱われています。
実際に証券口座を開設して投資を始めるまでの手順はシンプルです。まず証券会社のWebサイトから口座を開設し、マイナンバーカードや本人確認書類を提出します。その後、ログインして商品を選び、積立金額を設定するだけでスタートできます。NISA口座の開設やiDeCoの申し込みには時間がかかる場合もあるため、早めの手続きを心がけるとよいでしょう。
まとめ
個人事業主が老後に安心を得るためには、「国民年金だけでは不十分である」という現実を直視することが出発点です。そのうえで、小規模企業共済、iDeCo、新NISAといった制度を理解し、早めに投資・資産運用をスタートさせることが鍵になります。
収入に波がある個人事業主だからこそ、余剰資金を“貯金”ではなく“資産形成”に回す発想が必要です。老後の不安を“今”の行動で取り除き、未来に備えていきましょう。
参考情報・出典
- 日本年金機構「令和6年度の年金額」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/nenkinjoki/20150428.html - 中小企業基盤整備機構(小規模企業共済)
https://www.smrj.go.jp/kyosai/ - 金融庁「NISA制度の概要」
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/index.html - 金融審議会市場ワーキング・グループ報告書(2019年)
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20190603/01.pdf - 総務省統計局「家計調査年報(2022年)」
https://www.stat.go.jp/data/kakei/longtime/2022/index.html