物価上昇が家計を直撃しています。スーパーでの買い物も、電気代やガス代の請求書も、以前より明らかに高くなったと感じている方は多いでしょう。日本だけでなく、アメリカやヨーロッパをはじめとする各国でも、インフレが長期化の様相を見せ、生活コストの上昇はグローバルな課題となっています。
こうした状況の中、「資産形成の柱」として人気を集めているのが、米国のS&P500指数や全世界株式(オルカン)を対象としたインデックス投資です。では、生活費が高騰し続ける今、本当にS&P500やオルカンに投資していれば安心なのでしょうか?
今回の記事では、資産の成長が生活コストの上昇に追いつくのか、あるいはインフレ対策として機能するのか、投資初心者も中級者も気になるこの問いについて、データと実績をもとに検証していきます。
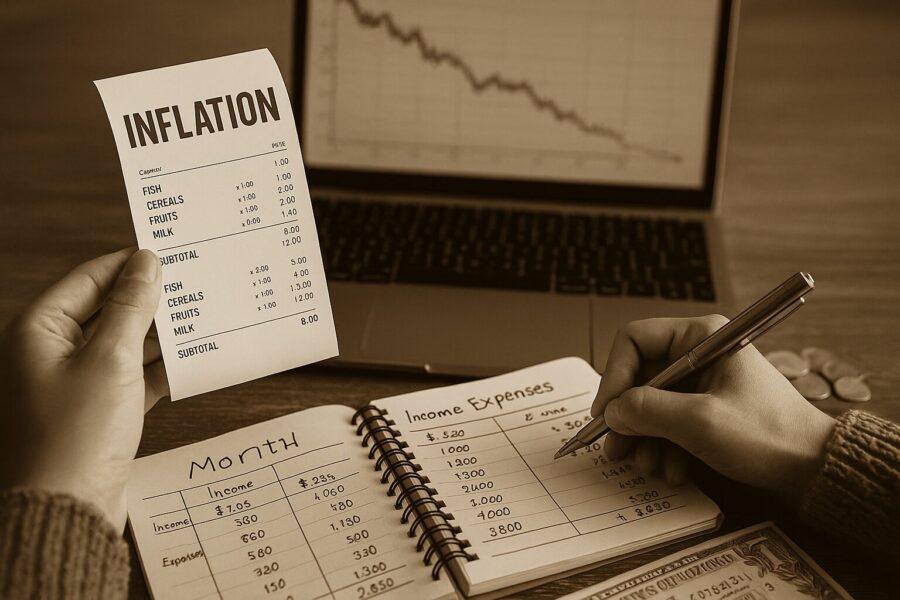
1. 生活費高騰で家計はどう変化?
ここ数年、消費者物価指数(CPI)の上昇は家計に直撃しています。2022年以降、世界的な資源価格の高騰や円安の影響も加わり、日本でもエネルギーや食品を中心に物価が急上昇しました。
1-1.低中所得層の家計の変化
総務省のデータによれば、日本のCPIは2022年に前年比約4%上昇し、2023年以降も2〜3%台で推移しています。これは過去30年間の物価上昇が1%未満だった日本にとっては異例の水準です。
特に打撃を受けているのが、低・中所得層の家計です。家計調査によると、可処分所得の中で「食料費」「光熱費」「交通費」などの生活必需支出が占める割合が増加しており、貯蓄に回す余力が減っている家庭が増加しています。
節約志向が高まる一方で、将来への備えとしての「投資」や「資産形成」を見直す動きも広がっています。
1-2.先進国におけるインフレの加速
また、世界的に見てもこの傾向は同様です。米国のBLS(労働統計局)のデータによると、アメリカのCPI上昇率は2022年に9%を超え、その後も5〜6%の高水準で推移。
ガソリンや住宅費、食品など生活必需品の価格上昇が顕著で、国民の購買力に大きな影響を及ぼしました。OECDが公開しているインフレ統計でも、2022年以降、ほぼすべての先進国でインフレが加速していることが確認できます。
1-3.現金を持つリスクが顕在化
このようなインフレ環境下では、「現金のまま持ち続けるリスク」が顕在化します。例えば、毎年2〜3%のインフレが継続した場合、10年でお金の価値は20〜30%目減りします。つまり、仮に100万円をタンス預金していても、10年後には70〜80万円程度の購買力しか持たないという計算です。
したがって、今こそ「お金の目減りに負けない投資」が重要なテーマになってきているのです。では、物価上昇に対抗する手段として、米国株(S&P500)や全世界株(オルカン)はどれほど有効なのでしょうか?
2. S&P500はインフレに勝てるのか
S&P500は、米国の代表的な株価指数であり、アップルやマイクロソフト、アマゾンなど、世界を代表する大企業500社の株価をもとに構成されています。米国経済の成長を反映しやすく、過去30年間で年平均7〜10%前後のリターンを記録してきました。
インフレ局面においても、S&P500は比較的高いパフォーマンスを発揮しています。たとえば、1970年代のスタグフレーション時代や、2022年の高インフレ期にも、一時的な調整はあるものの、中長期で見ると物価上昇を上回る成長を遂げています。米国企業の価格転嫁力や、成長セクターの台頭が背景にあるため、インフレヘッジ資産として一定の効果があると言えるでしょう。
一方で注意したいのは、「インフレと株価が常に連動するわけではない」という点です。インフレが急激に進行する場面では、FRB(米連邦準備制度)が利上げを行うことで景気が減速し、S&P500のようなリスク資産が短期的に下落するケースもあります。2022年の利上げ局面では、S&P500は年初から20%以上下落しました。
つまり、S&P500は長期的にはインフレを超える成長が期待できるが、短期的には値動きが激しいリスク資産であるという点を理解しておく必要があります。
3. オルカンの分散効果と実力
オルカン(全世界株式インデックス)は、MSCI ACWI(All Country World Index)をベンチマークとする投資信託で、米国・欧州・日本・新興国など、約50か国の株式市場に広く分散投資するのが特徴です。
3-1.大きな打撃を与えにくい
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)などを通じて投資が可能で、一本で世界経済の成長に乗れる設計となっており、初心者から上級者まで幅広く支持されています。
特にインフレ時の投資先として注目されるのは、地域によって景気の波が異なるため、一部地域の経済悪化が全体に大きな打撃を与えにくいというメリットがあるからです。
例えば、米国がリセッションに陥ったとしても、インドや東南アジアなど新興国の成長が相殺してくれる可能性があります。さらに、為替ヘッジを行わない商品が多いため、円安の局面では為替益も取り込めるという特徴もあります。
3-2.安定性はS&P500より高い
ただし、全世界株式は構成比率の約60%を米国株が占めており、結果的にS&P500との値動きが類似する場面も多いです。とはいえ、地域・通貨・業種の分散が効いているため、長期的な安定性はS&P500よりも高いと評価されることもあります。
4. 投資信託の積立は継続すべき?
生活費が上がると、「毎月の積立がきつい」「一旦やめたほうがいいのでは」と感じる方もいるでしょう。しかし、インフレ時こそ、積立投資の継続は極めて重要です。理由は2つあります。
4-1.現金価値の目減り
一つ目は、「インフレ=現金価値の目減り」であること。現金で保有しているだけでは購買力が下がっていくため、インフレを上回る成長が期待できる資産へ投資する必要があります。
4-2.ドルコスト平均法の効果
二つ目の理由は、「ドル・コスト平均法」の効果です。価格が下がったときも一定額を投資し続けることで、平均購入単価を下げ、将来のリターンを高める効果が得られます。
もちろん、無理をして生活が破綻するようでは本末転倒です。支出の見直しを図り、積立額を一時的に減らすことは問題ありません。ただし、完全に積立を停止してしまうと、将来の資産形成に大きな差が出る可能性があるため、少額でも継続することが推奨されます。
オルカンやS&P500に連動する投資信託は、長期保有によって「複利効果」が積み上がり、20年後、30年後に大きな差となって表れます。インフレを乗り越えるには、今できる小さな積立が、将来の安心につながるのです。
5. まとめ:頼れる資産形成の軸とは
生活費が上昇し、家計のやりくりが難しくなる中でこそ、投資の重要性が増しています。S&P500やオルカンは、物価上昇にも一定の耐性を持ち、長期的には実質資産を増やす可能性があります。
短期的な変動に一喜一憂せず、コツコツと積立を続ける姿勢が、将来の安心につながるでしょう。現金の価値が下がり続ける時代、頼れるのは「未来への投資」かもしれません。
参考文献
- eMAXIS Slimシリーズ 公式サイト
https://emaxis.jp/lp/slim/ - MSCI公式 All Country World Index データ
https://www.msci.com/documents/10199/cb3c74c3-625b-3e56-3d12-9fc4c123db66 - J.P.モルガン Guide to the Markets(日本語版)
https://am.jpmorgan.com/jp/ja/asset-management/adv/insights/market-insights/guide-to-the-markets/ - 野村アセットマネジメント マーケットレポート
https://www.nomura-am.co.jp/market/report/ - 米国労働統計局(BLS)CPI統計
https://www.bls.gov/cpi/ - OECDインフレデータ
https://data.oecd.org/price/inflation-cpi.htm - マネックス証券コラム
https://info.monex.co.jp/news/2023/20230317_01.html





