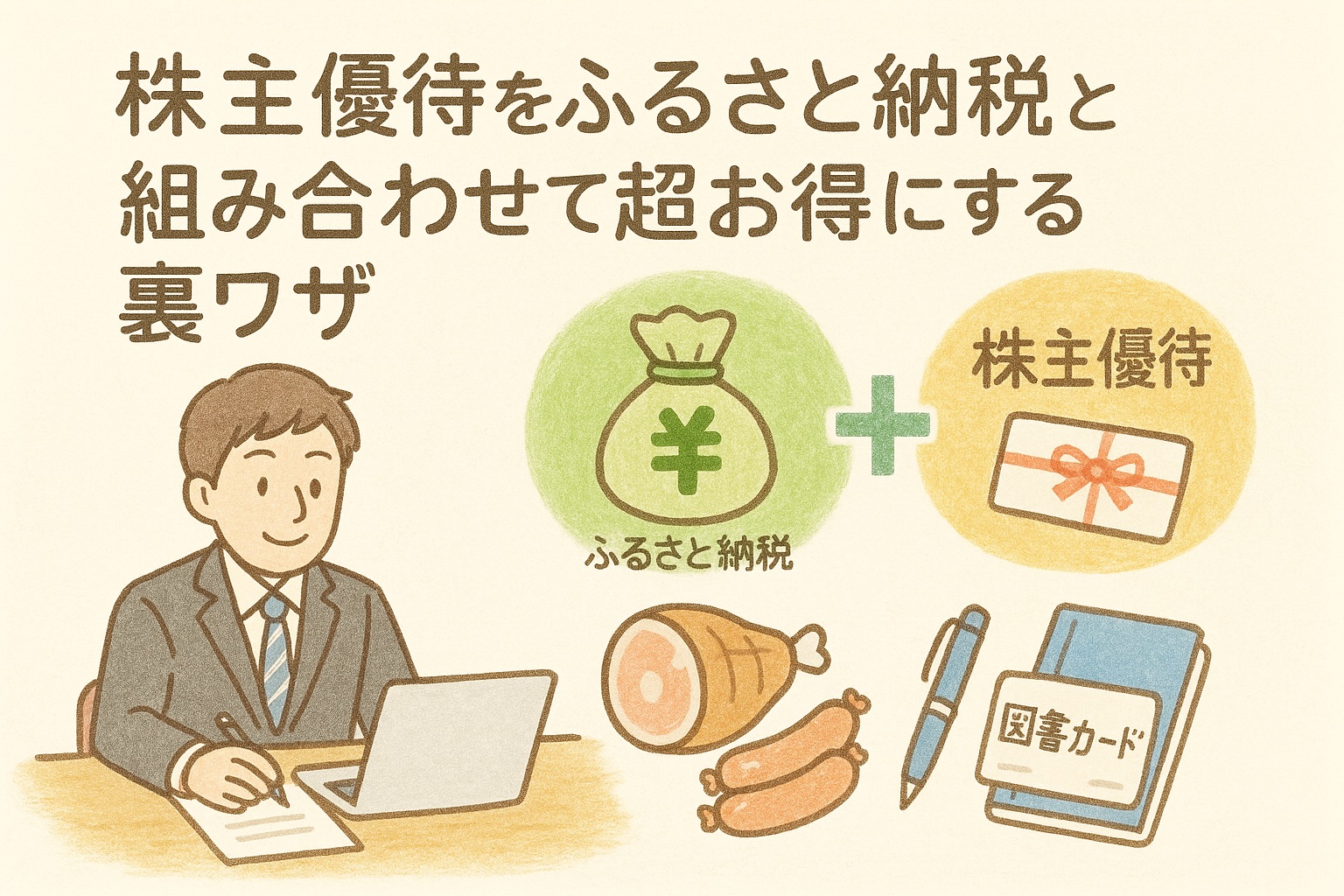
「株主優待」と「ふるさと納税」、この2つの制度はそれぞれ単体でも十分にお得な制度として知られていますが、組み合わせて活用することで、その効果は飛躍的に高まります。日々の生活費を削減しつつ、税負担の軽減にもつなげられる絶好の方法です。
株主優待では、飲食や日用品、ビジネス書籍など、仕事とプライベート両面で使える特典を得ることができます。一方のふるさと納税では、税金の一部を地方に寄付することで、食品や雑貨などの返礼品を実質的な“節税効果”とともに受け取ることが可能です。
本記事では、まず、株主優待とふるさと納税の組み合わせで得られるメリットを解説したうえで、実際に経費削減に役立つ優待銘柄を5つご紹介します。すでに両制度を活用している方にも、新たな発見がある内容となっています。
1. 株主優待とふるさと納税の相乗効果とは?
株主優待とふるさと納税は、一見するとまったく別の制度に思えますが、実際には非常に高い親和性を持っています。共通しているのは「現金を使わずにモノやサービスを手に入れる」という点です。
例えば、株主優待で外食費や日用品をまかない、浮いた支出分をふるさと納税に回せば、実質2000円の負担でさらなる物品を受け取ることができます。この“浮いたお金の再投資”こそが、相乗効果の鍵となります。
また、株主優待で得られる金券やクーポンを活用すれば、生活コストを可視化しやすくなるメリットもあります。ふるさと納税側でも、返礼品の中に事業で使える備品や消耗品が多く存在するため、業務用アイテムの調達先としても優秀です。
例えば、トイレットペーパーやコピー用紙、ボールペンなど、意外と出費がかさむものを賄うことで、実質的なキャッシュアウトを抑えることが可能になります。
このように、優待と納税の「現物支給+税制優遇」という組み合わせは、現金ベースでの節約と税務上のメリットの両面を持つ非常に合理的な手法だといえるでしょう。
2. 経費削減に使える株主優待5選【実用重視】
ふるさと納税との相乗効果を最大限に活かすためには、実際に日常や業務で使える株主優待を選ぶことが重要です。ここでは、「本当に使える」優待銘柄を5つご紹介します。
日用品や食品、事務用品など、現金支出を確実に減らすことができる優待ばかりです。ぜひ、参考になさってください。
パイロットコーポレーション(7846)
まず、注目したいのが、パイロットコーポレーション(7846)です。同社は世界的な筆記具メーカーとして知られており、株主優待では自社の高品質な文房具セットが贈られます。優待内容は年によって異なりますが、万年筆、ボールペン、シャープペンシル、ノート類など、業務に必要な筆記用具が揃います。
見た目にも高級感があるため、商談や打ち合わせで使っても恥ずかしくなく、実務での使用頻度が高い人には非常に重宝する優待です。
進学会ホールディングス(9760)
進学会ホールディングス(9760)の図書カード優待では、1,000円相当の図書カードが贈られます。図書カードは全国の多くの書店で使えるため、ビジネス書や専門書、業界誌の購入に便利です。
特に情報収集や自己研鑽を欠かせない職種の方にとっては、実質的に書籍代が浮く形となり、学習コストを抑えることができます。もちろん、書籍購入は必要経費としても計上しやすく、節税との相性も良好です。
日本ハム株式会社(2282)
三つ目は、日本ハム株式会社(2282)の自社製品詰め合わせ優待です。内容は年によって異なりますが、ハムやソーセージ、レトルト食品など、保存性に優れた食品が中心となっています。食費の一部をまかなえるだけでなく、仕事が忙しいときの簡易食にもなるため、効率的な生活をサポートします。
食費が浮いた分をふるさと納税に回すことで、さらに食品や日用品を獲得できるなど、キャッシュフロー改善にもつながります。
ダイドーグループホールディングス(2590)
同社は缶コーヒーや清涼飲料水で知られる大手飲料メーカーで、株主優待として年に一度、詰め合わせセットが届きます。コーヒーやお茶、ジュースなどは、オフィスに常備しておけば来客対応にも便利ですし、外出時に持ち歩けばコンビニでの出費を抑えられます。
自宅兼事務所のような環境でも役立ち、個人事業主の細かなコスト削減に貢献してくれるでしょう。
アルコニックス株式会社(3036)
非鉄金属を中心とした専門商社である同社は、株主優待として全国各地の名産品カタログギフトを提供しています。株数や保有期間によって内容が異なりますが、雑貨や食品、生活用品などから選べるため、自分のニーズに応じたアイテムを入手できる点が魅力です。
特に日常的に消費する品や、ふるさと納税で補いきれないものを選ぶことで、生活の無駄な支出をさらに減らすことができます。
以上の5つの株主優待は、いずれも単なる贅沢品ではなく、仕事や日常に直接役立つ“実用品”ばかりです。優待を活用して出費を抑えた分を、ふるさと納税に回すことで返礼品をさらに手に入れられるため、現金支出を最小限にしながら満足度の高い生活が実現できます。このダブル活用こそが、個人事業主にとっての賢い経費削減術といえるでしょう。
3. 個人事業主が得する具体的活用法
株主優待とふるさと納税の組み合わせは、単に「お得そう」というだけでなく、きちんと戦略的に使うことで大きな効果を発揮します。特に個人事業主にとっては、日常の支出管理と節税を両立できる点が最大の魅力です。
まず、活用の基本として意識したいのは、「浮いた出費の再投資」です。たとえば、株主優待で筆記具や食品を手に入れた場合、それによって支出が減る分をふるさと納税の寄付に回すという考え方です。
そうすることで、節税効果を享受しながら、さらに返礼品が得られるという“二重取り”のような形になります。
次に、優待とふるさと納税で得る品の役割を明確に分けておくこともポイントです。株主優待は「業務で確実に使う物」に集中し、ふるさと納税は「生活を支える品」や「事務所の備品」に充てるなど、用途の重複を避けると無駄がありません。
例えば、優待でボールペンやノートを補い、ふるさと納税でトイレットペーパーやお米を手に入れるというように、役割を分けて組み合わせると効果的です。
また、スケジュール管理も重要です。株主優待は権利確定日が年1〜2回に限定されていることが多いため、購入タイミングを逃さないように注意が必要です。
同様に、ふるさと納税も年末が締め切りとなるため、年間の収入見込みを早めにシミュレーションし、控除上限額を超えないように計画的に使いましょう。
このように、制度ごとの特性とスケジュールを理解し、計画的に「現物支給×税控除」を活かすことで、個人事業主にとっては非常に実用的かつ効率的な経費削減が可能になります。
まとめ
株主優待とふるさと納税を組み合わせることで、個人事業主は日々の出費を大幅に抑えつつ、税金対策も同時に進めることができます。どちらも「使えば得をする」制度ですが、無計画に使っていては効果が半減してしまいます。
今回ご紹介したように、文具、食品、飲料、書籍など、実務や生活に役立つ優待を賢く選び、ふるさと納税とバランスよく組み合わせることで、キャッシュアウトを最小限に抑えることができます。支出のコントロールは、事業の安定運営にも直結します。
今後さらにインフレや物価上昇が続く中で、こうした制度を戦略的に活用できるかどうかは、事業者としての生存力にもつながっていくでしょう。今年こそは、「節税×節約」を同時にかなえる優待活用術を、自分の事業に取り入れてみてはいかがでしょうか。
参考文献
- 国税庁「ふるさと納税」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1155.htm - パイロット「株主優待制度」 https://corp.pilot.co.jp/ir/stock/yutai.html
- 進学会「IR情報」 https://www.shingakukai.co.jp/ir/index.html
- 日本ハム「株主優待情報」https://www.nipponham.co.jp/ir/stock_info/yutai/
- ダイドー「DyDoの株主のメリットは?」https://www.dydo-ghd.co.jp/individual/benefits/
- アルコニックス「株主優待」https://www.alconix.com/ir/stock/benefit/





