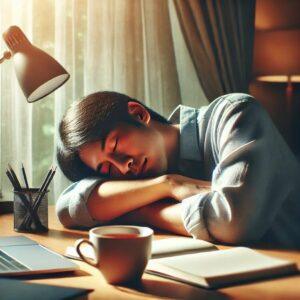食料品、日用品、外食…私たちの生活に欠かせないあらゆるモノの価格がじわじわと上昇し続けています。インフレが続く中で、支出を抑える方法を探している方も多いのではないでしょうか。
そんな方におすすめなのが「株主優待」を活用することです。株主優待は、企業が株主に向けて自社商品やサービスを提供する仕組みで、うまく活用すれば現金支出を減らしながら物価上昇の影響を和らげることができます。
本記事では、インフレ時代にこそ注目したい株主優待の活用方法と、特に節約に役立つ優待銘柄を厳選してご紹介します。
1. 物価高でも安心!優待の活用術
インフレとは、簡単に言えばモノやサービスの価格が上がり、お金の価値が下がることです。たとえば、以前は1,000円で買えた日用品が1,200円に値上がりしているとすれば、それはインフレが家計を圧迫しているサインです。
個人事業主にとっては、こうした日常的な出費が積み重なることで利益が目減りしてしまうリスクがあります。
そこで注目すべきが、「株主優待」です。企業によっては、一定の株数を保有している株主に対し、配当金とは別に自社の商品や割引券、ギフト券などを提供しています。優待をうまく活用すれば、現金を使わずにモノやサービスを得ることができ、実質的に支出を抑えることが可能になります。
特に、「現物」や「定額サービス」を提供する優待は、インフレ時にも価値が目減りしにくいという強みがあります。たとえば、「ハンバーガーセット1つ」のように商品単位で提供される優待は、価格が上がっても内容は基本的に変わらないため、物価が上昇すればするほど相対的な価値は高まります。
また、節約志向の高い人にとって、日用品や食料品の支出を優待で補えることは大きな魅力です。実際に使える銘柄を選べば、家計の見直しに直結します。
2. 物価上昇に効く!優待銘柄ベスト5選
インフレ対策として有効な株主優待の中でも、実際に活用しやすい5銘柄を厳選しました。すべて「現物支給」または「実用性の高いサービス」を提供しており、日常生活や仕事の経費削減に直結する内容となっています。ぜひ、ご参考になさってください。
日本マクドナルドホールディングス(2702)
マクドナルドの優待は、バーガー・サイドメニュー・ドリンクを組み合わせた無料引換券がもらえる内容です。100株保有で年2回、6枚ずつ発行されます。
外出時のランチや家族での食事など、食事代の節約に直結します。物価が上がっても「セット1つ分」がもらえる形式のため、インフレ時にこそ威力を発揮します。
クリエイトSDホールディングス(3148)
神奈川県を中心に展開するドラッグストアで、優待内容は店舗で使える買物券です。医薬品だけでなく、食品や日用品も扱っており、優待券を使えば節約になります。
店舗の無い地域に住んでいる株主は、お買物券の代わりにお米券を受け取れます。おこめ券は全国のスーパーでも使えるため、使い勝手も抜群です。
キャンドゥ(2698)
100円ショップ大手のキャンドゥでは、100株保有で優待券2,000円分(税別)を年1回受け取れます。日用品や文房具、収納用品など、事務所で必要な消耗品をカバーできます。特に物価高騰が続く今、100円という価格を維持する店舗で使える点は経費管理の強い味方になります。
サンリオ(8136)
自社のテーマパーク「サンリオピューロランド」などの入場券と、グッズ購入に使える1,000円分の優待券がセットでもらえます。入場料が上がっても「入場券1枚」は変わらず利用できるため、コストが固定化されるメリットがあります。
かどや製油(2612)
こちらは、ごま油を中心とした調味料セットがもらえる優待です。料理に使う油は価格変動が激しいため、優待でまかなえるとかなりの節約になります。料理する人にとっては、調味料の補填として非常に有効です。値上がりが続く中でも、安定して品質の高い調味料が得られるのはありがたいポイントです。
3. 優待選びの注意点と賢い使い方
株主優待は非常に魅力的な制度ですが、選び方や使い方を間違えると期待した効果を得られないこともあります。特に、インフレ対策と節約を目的とするには、実用性とリスクのバランスを意識することが重要です。
ここでは、優待の選び方についての注意点をご説明しますので、ぜひ参考にしてください。
実用的かどうか
まず大切なのは、「優待が自分の生活で本当に使えるかどうか」です。例えば、レジャー施設の無料券がもらえる優待でも、頻繁に行かない施設であれば意味がありません。実際に利用する場面を想像し、「現金で支払うはずだった費用が浮くかどうか」という視点で選ぶと、節約効果の高い優待が見えてきます。
改悪や廃止
次に注意したいのが、優待制度の「改悪」や「廃止」です。企業業績や経営方針の変更により、優待内容が縮小されたり、突然なくなったりするケースも珍しくありません。特に最近は、優待のコストを嫌い制度を見直す企業も増えているため、保有前に公式IRやニュースで状況を確認しておきましょう。
株価の変動リスク
また、株主優待を目的に株を保有する場合でも、株価の変動リスクは避けられません。株価が大きく下がって含み損が出れば、いくら優待が魅力的でも損益はマイナスになります。できるだけ財務基盤が安定している企業や、配当も出している企業を選ぶと、トータルでのリターンが安定します。
長期保有特典があるか
さらに注目すべきなのは、「長期保有特典」です。一部の企業では、1年以上保有した株主に対して優待内容をグレードアップする制度があります。売買を繰り返すよりも、信頼できる企業の株を継続保有したほうが、より多くの恩恵を受けられることもあります。
最後に、優待の利用には有効期限がある場合が多いため、届いたら早めに使う習慣を持つとよいでしょう。使いそびれて無駄にしてしまえば本末転倒です。優待スケジュールや期限をカレンダーに記録するなど、管理面でも工夫が必要です。
まとめ
物価上昇が続くなか、株主優待は強力なコスト削減ツールになります。ハンバーガーセット、日用品、文房具、ごま油など、現金支出を直接減らせる優待は、経営を支える実利となります。特に今回紹介した5つの銘柄は、日々の支出を無理なく抑えられる実用的な内容ばかりです。
ただし、優待には注意すべき点もあります。実際に使える内容か、制度が安定しているか、株価や配当とのバランスはどうかといった観点で、冷静に銘柄を選びましょう。
安易に「優待が豪華だから」という理由だけで飛びつくのではなく、自分にとって価値のあるものかを基準にすることが、賢い株主優待活用法です。
インフレに強く、実益もあり、かつ楽しめる。それが株主優待の大きな魅力です。この仕組みをうまく活かして、物価高の時代をしたたかに、そして楽しく乗り越えていきましょう。
参考文献
- トウシル「優待弁護士厳選!インフレ対抗!生活応援優待ベスト10」https://media.rakuten-sec.net/articles/-/44586
- トウシル「家計のお助け、インフレに負けない優待銘柄」https://media.rakuten-sec.net/articles/-/40506
- ダイヤモンドZAI「「インフレになると儲かる日本株&米国株」を紹介!海外の金利上昇でも儲かる「三菱UFJFG」、海外旅行が増えると利息収入が増える「マスターカード」に注目!」https://diamond.jp/zai/articles/-/297129