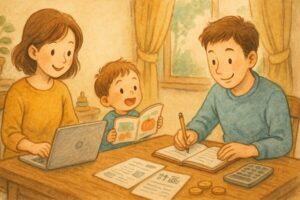近年、世界はパンデミック、気候変動、地政学的リスクなど様々な危機に直面しています。こうした環境下で、これまで企業経営の金字塔とされてきた「極限までの効率化」という考え方に疑問符が投げかけられるようになりました。
本記事では、「戦略的非効率」とも呼べる冗長性の確保が、いかに企業のレジリエンス(回復力)を高め、持続可能な成長をもたらすかについて解説します。ぜひ、最後までご覧ください。
1. 「効率性の罠」から脱却する新時代の経営戦略
かつて、企業経営において最も重視されてきたのは「効率性」でしたが、ジャストインタイム生産方式や在庫最小化など、無駄を徹底的に排除するリーン経営が理想とされてきました。
しかし、2020年のパンデミックや2022年の世界的なサプライチェーン混乱は、この考え方の脆弱性を浮き彫りにしました。
経済評論家の佐々木一寿氏は、ナシーム・タレブの「反脆弱性」という概念を引用し、単に「頑強」であるだけでなく、衝撃を糧にして成長できる「反脆さ」を持つ組織が求められていると指摘しています。
タレブによれば、「反脆さは耐久力や頑健さを超越する。耐久力のあるものは、衝撃に耐えて現状をキープするが、反脆いものは衝撃を糧にする」とのことです。
『効率性の罠』の具体例としては、コスト削減のため単一サプライヤーに依存した自動車メーカーが半導体不足で生産停止を余儀なくされたケースや、極端な在庫削減を進めた小売業が需要急増時に商品欠品を起こしたケースがあります。
また、固定費削減のため正社員を減らした企業が経済回復期の人材獲得競争で苦戦したケースなども挙げられます。
このような状況を踏まえると、戦略的非効率とは、効率性の罠から脱却し、意図的に冗長性、つまり、余剰を持たせることで、不確実性の高い環境下でも事業継続性を確保する考え方だと言えます。
それは、単なる「無駄」ではなく、組織の生存と繁栄のための「戦略的投資」なのです。
2. 冗長性がもたらす企業レジリエンスの真価
冗長性とは、同じ機能を持つ要素を複数用意しておくことで、一部が故障しても全体としては機能を維持できる性質を指します。この考え方は、もともと工学や情報システムの分野で発展してきましたが、今や企業経営全体に応用されるべき概念となっています。
世界経済フォーラムの「グローバルリスク報告書2025」によれば、今後10年間で最も深刻なリスクとして「異常気象」「国家間の武力紛争」「生物多様性の喪失」などが挙げられています。
こうしたリスクに対応するためには、企業も冗長性を備えたレジリエントな体制を構築する必要があります。
冗長性の具体的な形としては、単一の調達先に依存せず、複数の地域や企業から調達するサプライチェーンを多様化し、緊急時に備えた余剰資金の保有といった財務バッファの確保することです。
また、一人が複数の業務をこなせるようにする人材の多能工化、そして中央集権的ではなく各部門が一定の権限を持つ分散型の意思決定構造などが挙げられます。
日本では、中小企業庁が「事業継続力強化計画」認定制度を設け、企業のレジリエンス強化を後押ししています。この制度を活用する企業には税制優遇や金融支援が提供されており、多くの企業がレジリエンス強化に取り組んでいます。
実際、2011年の東日本大震災の際、事前に冗長性対策を講じていた企業は、そうでない企業と比べて復旧速度が平均で40%速かったというデータもあります。
このことから、冗長性への投資は単なるコストではなく、長期的な経営戦略として重要であることが示されています。
3. 戦略的余剰が危機に強い組織をつくる
戦略的冗長性の導入は、単にリスク対策というだけでなく、組織の創造性や適応力も高める効果があります。
Diamond Harvard Business Review(ダイアモンド・ハーバード・ビジネス・レビュー)の研究によると、適度な『遊び』や『余裕』を持つ組織では、従業員のクリエイティビティやウェルビーイングが向上し、結果的にイノベーション創出につながるという報告もあります。
これは、脳科学の観点からも説明できます。常に効率性を追求し、余裕のない状態(ベータ波状態)では、脳は新しいアイデアを生み出しにくくなります。
一方、適度な余裕がある状態(アルファ波やシータ波状態)では、創造的な思考が促進されます。実際、多くの革新的なアイデアが生まれるのは、仕事中ではなく『余白の時間』であることが研究から明らかになっています。
戦略的余剰を効果的に取り入れるポイントとしては、将来の変化に対応するための意図的な冗長性の計画的導入、過剰な冗長性はコスト増大につながるため適度なバランスを取ることです。
また、『効率至上主義』から『レジリエンス重視』への価値観の転換を組織全体で共有することなども挙げられています。
成功事例としては、東日本大震災後に『リスク対応型調達戦略』を導入し、重要部品のサプライヤーを複数化して地理的にも分散させたトヨタ自動車、事業ポートフォリオの多様化を戦略的に進め、一部事業が苦境に陥っても全社的には安定した経営を維持しているソニーなどがあります。
これらの企業は、意図的な冗長性の確保により、経営環境の激変にも柔軟に対応できる体制を構築しています。
まとめ:バランスの取れた「戦略的非効率」が未来を拓く
今後の企業経営において重要なのは、効率性と冗長性のバランスです。極端な効率化でもなく、闇雲な余剰でもない「戦略的非効率」の導入が、不確実性の時代を生き抜くカギとなります。
タレブが言うように、単に「頑強」であることを超えて「反脆い」組織、つまり危機を糧に成長できる組織こそが、これからの時代に求められています。そのためには、意図的な冗長性の導入と、それを支える組織文化の醸成が不可欠です。
効率性と冗長性は、一見すると相反する概念のように思えますが、実は持続可能な経営のための両輪なのです。明日の危機に備えながら、今日の競争力も高める—そんな「戦略的非効率」の考え方が、これからの企業経営の新たな指針となるでしょう。
企業がこれから取り組むべき具体的なステップとしては、極度の効率化によってリスクが高まっている領域を特定する自社の脆弱性の評価や、事業継続に最も重要な領域から段階的に冗長性を導入する優先順位付けです。
また、冗長性への投資リターンを長期的視点で評価する枠組みの構築や、「戦略的余剰」の価値を社内で共有し短期的効率性のみを評価する文化を変えることなども、企業が取り組むべきステップになるでしょう。
今後は、中小企業庁の「事業継続力強化計画」のような公的支援制度も活用し、自社のレジリエンス強化を図ることをお勧めします。予測不能な時代だからこそ、「想定外」を「想定内」に変える冗長性の確保が、企業の持続的発展には不可欠なのです。
参考文献
- 企業の競争優位につながる「これからのオペレーション」の条件 https://dhbr.diamond.jp/articles/-/10059
- グローバルリスク報告書2025年版:紛争、環境、偽情報が最大の懸念 https://jp.weforum.org/press/2025/01/global-risks-report-2025-conflict-environment-and-disinformation-top-threats-0c7718806f/
- 事業継続力強化計画 – 中小企業庁 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/keizokuryoku.html
- ブラック・スワンへの対処法「反脆弱性」とは何か? https://diamond.jp/articles/-/224579
- 「畏敬の念」が個人と組織のレジリエンスを高める https://dhbr.diamond.jp/articles/-/8052
- 遊び心こそが組織のレジリエンスと従業員のウェルビーイングを高める https://dhbr.diamond.jp/articles/-/10908