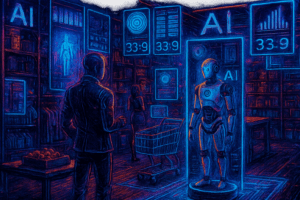共働き家庭にとって、夫婦それぞれが仕事を持つ一方で家計のやりくりや子育て、介護などの負担は増えるばかりです。しかし、税制改正による基礎控除の引き上げや配偶者控除・配偶者特例の見直し、住宅ローン控除や医療費控除といった各種優遇制度を適切に活用すれば、年間で数十万円レベルの節税効果が期待できます。本記事では、最新の税制改正ポイントを踏まえつつ、働きながら無理なく申請できる控除の概要と手続き方法、申請時の注意点までをわかりやすく解説します。知らないままでは損をしてしまう優遇措置を最大限引き出し、家計にゆとりをもたらしましょう。

1.共働き家庭が得する税制優遇の概要解説
共働き世帯は世帯収入が増える反面、所得税・住民税の負担率が高くなる傾向があります。特に年収が一定水準を超えると、配偶者控除や扶養控除の対象から外れ、結果として手取りが思ったほど増えないケースも少なくありません。そこで注目したいのが、令和7年度以降に実施された大幅な基礎控除の引き上げや配偶者特例の緩和です。基礎控除額が拡充されたことで、夫婦それぞれの所得に関わらず、一定額までは所得税・住民税が軽減されるようになりました。
さらに、配偶者控除・配偶者特別控除の適用範囲が見直され、年間収入の上限が引き上げられたことで、これまでは控除対象とならなかったパート収入にも恩恵が及ぶケースが増えています。住宅ローン控除や医療費控除、育児・介護休業取得時の控除など、世帯収入に応じて適用できる制度は多岐にわたります。これらを組み合わせることで、共働き家庭は実質的な税負担を大きく抑えられるのです。
本ガイドでは、こうした優遇措置を「知っているだけ」で終わらせず、「実際に申請する」までをサポートします。各制度の適用要件や申請タイミング、確定申告や年末調整での手続き方法と必要書類、注意点などを詳しく解説しますので、まずはここで全体像をつかみ、以後の各章で具体的なポイントを押さえていきましょう。
2.配偶者控除・配偶者特例制度の活用方法
2-1.年収要件と控除額の仕組み
配偶者控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下かつ配偶者の合計所得金額が48万円以下で最大48万円が所得控除されます。共働き家庭では、パート勤務などで配偶者の年収が103万円以下に収まる場合、フルで控除を受けられるケースが多いでしょう。一方、配偶者特別控除は配偶者の合計所得が48万円超から150万円以下の範囲で、所得額に応じて控除額が段階的に縮小しつつ適用されます。これにより、104万円以上150万円前後までのパート収入でも部分的に控除が受けられるようになり、手取り減を抑えつつ収入アップを図れます。
2-2.控除対象拡大の改正ポイント
令和7年度の税制改正では、配偶者特別控除の適用限度額が見直され、従来の年収150万円程度からさらに引き上げられる方向が議論されています。今後、配偶者が年収160〜180万円まで所得控除対象に含まれる可能性があり、共働き世帯の節税余地が拡大する見込みです。最新の制度改正情報をチェックし、来年度以降のパートシフトや扶養内調整を行うことで、税負担を最小化しながら家計収入を最大化できます。
3.住宅ローン控除・医療費控除など優遇制度解説
3-1.住宅ローン控除の基本と共働きメリット
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、年末のローン残高の1%(最大控除額40万円程度)が最長10年間にわたり所得税から控除される制度です。共働き家庭では、夫婦それぞれが住宅ローン名義人になる“ペアローン”を組むことで、控除総額が2人分適用されるケースがあります。ただし、ペアローンを利用する際は借入金割合や借入期間、金融機関選びに注意が必要です。
3-2.医療費控除とその他の控除
医療費控除は、1年間に家族で支払った医療費が10万円(または総所得金額等の5%)を超えると、超過額が所得控除の対象になります。歯科矯正や通院交通費も含まれるため、子どもの予防接種や通院記録を整理しておくことがポイントです。そのほか、ふるさと納税による寄附金控除、小規模企業共済掛金控除、生命保険料控除など、共働き世帯が利用しやすい優遇措置を組み合わせれば、所得税と住民税をさらに減らせます。
4.手続き方法と申請時に気を付けるポイント
4-1.年末調整と確定申告の使い分け
会社員の場合、配偶者控除や生命保険料控除、住宅ローン控除(初年度)などは年末調整で申請できます。医療費控除や住宅ローン控除2年目以降、小規模企業共済などは確定申告が必要です。年末調整だけでは申請漏れが起こりやすいため、11月頃から必要書類の準備を始め、翌年2月中旬までに忘れずに申告しましょう。
4-2.必要書類と注意点
以下の書類を事前にまとめておくとスムーズです
- 源泉徴収票(本人・配偶者)
- 住宅ローン残高証明書
- 医療費の領収書および明細書
- 生命保険料・個人年金保険料の控除証明書
- マイナンバー通知書またはカード
申請時には、控除額の計算ミスや添付漏れが最も多いトラブルです。控除証明書は原本提出か、電子申告時のスキャン添付を忘れず、申告書の控除欄と計算結果が一致しているか必ず確認してください。
5.まとめ
共働き家庭は、配偶者控除・配偶者特別控除、住宅ローン控除、医療費控除など多彩な優遇措置を活用することで、年間数十万円単位の節税が可能です。令和7年度改正ポイントを押さえ、年末調整と確定申告を適切に使い分けることが重要です。必要書類を整理し、申請漏れや計算ミスを防ぐことで、家計にゆとりを生み出しましょう。税制優遇を最大限活用し、働く夫婦の家計管理を効率化してください。
参考文献
【令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について】
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
【配偶者控除廃止はいつから?2025年の制度改正と103万円の壁】
https://www.freee.co.jp/kb/kb-payroll/spousal-exemptions-abolished/
【共働きの場合の定額減税による手取り額-具体例を用いて解説】
https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/73690/
【令和7年度税制改正大綱から見る年収103万の壁について】
https://www.chuo-tax.jp/b-tax/1342.html
【結婚で税金が安くなるって本当?共働きの場合は?FPが解説する】
https://manekomi.tmn-anshin.co.jp/kakei/17502631