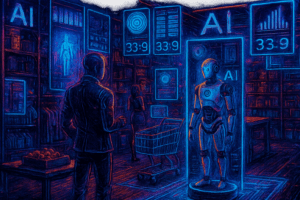企業における福利厚生や手当は、社員の働きやすさや満足度を向上させる重要な要素です。しかし、多くの社員が「福利厚生と手当の違いが分からない」「どんな手当が使えるのか知らない」という課題を抱えています。本記事では、福利厚生と手当の違いを明確にし、見落としがちな手当について詳しく解説します。知らないと損をする可能性もあるため、ぜひ最後まで読んで、自分の職場にある制度を最大限活用しましょう。

1. 福利厚生と手当の違いを正しく理解しよう
まず、福利厚生と手当の違いを整理しましょう。これらの言葉は似ていますが、支給の目的や仕組みが異なります。
1-1. 福利厚生とは?
福利厚生とは、企業が従業員の生活をサポートするために提供する制度やサービスの総称です。給与や賞与とは別に、従業員が快適に働ける環境を整えるために支給されます。主に法定福利厚生と法定外福利厚生の2種類に分類されます。
法定福利厚生は法律で企業に義務付けられているもの(社会保険、雇用保険、労災保険など)、法定外福利厚生は企業が独自に提供する福利厚生(住宅補助、社員食堂、育児支援、健康診断補助など)です。
福利厚生の最大の特徴は、基本的にすべての従業員が平等に受けられることです。例えば、健康診断の費用補助や社員割引などは、社員であれば誰でも利用できるものが多いです。
1-2. 手当とは?
一方で、手当とは、特定の条件を満たした従業員に対して支給される金銭的な報酬のことです。福利厚生が「すべての従業員に対するサービス」であるのに対し、手当は「特定の条件を満たす従業員に対する追加報酬」と言えます。
手当には、法律で義務付けられている手当(時間外手当、休日手当、深夜手当など)と、企業が独自に設定する手当(通勤手当、住宅手当、家族手当、役職手当など)があります。
例えば、「住宅手当」は、賃貸物件に住んでいる社員には支給されることが多いですが、実家暮らしの社員には支給されないこともあります。このように、手当は一定の条件を満たす場合のみ支給される点が特徴です。
1-3. 福利厚生と手当の使い分け
企業は、採用力や従業員の定着率向上のために福利厚生を充実させ、一方で個々の事情に応じた支援として手当を用意しています。求職活動の際には、自分がどのような手当を受けられるのか、福利厚生の内容と合わせて確認することが重要です。
2. 知らないと損!意外と使える手当の種類
手当には、広く知られているものと、あまり知られていないが活用すると大きなメリットがあるものがあります。ここでは、意外と見落とされがちな手当を紹介します。
2-1. 通勤手当
多くの企業で支給されている通勤手当ですが、支給基準は会社によって異なります。一部の企業では、定期代ではなく実際の通勤費を申告すれば支給額が増えるケースや、自転車通勤者向けの手当があることもあります。特に在宅勤務が増えている企業では、新しい通勤手当のルールが適用されている可能性があるため、確認してみましょう。
2-2. 住宅手当
賃貸物件に住んでいる場合、企業によっては住宅手当が支給されることがあります。企業の中には、家賃の30%まで補助するケースや、一定の地域に住むことで手当を増額する制度を採用しているところもあります。地方転勤者向けの家賃補助などもあるため、転勤を伴う職場の人は特に確認すべき手当です。
2-3. 家族手当・扶養手当
配偶者や子供がいる従業員向けに支給される家族手当や扶養手当も、企業によって基準が異なります。支給対象となる扶養の範囲や、配偶者の収入条件などをチェックすることで、申請可能な場合があるため、事前に確認しておきましょう。
2-4. 資格手当
業務に関連する資格を取得すると支給される資格手当は、多くの企業で導入されています。資格取得費用を補助する企業もありますが、すでに取得済みの資格が手当の対象になっている可能性もあるため、一度社内規程を見直してみましょう。
2-5. 在宅勤務手当
リモートワークが増えたことで、新たに導入された「在宅勤務手当」も要チェックです。光熱費や通信費の補助が含まれている場合があるため、リモートワークの多い人は特に確認することをおすすめします。
2-6. 出張手当
出張が多い仕事に従事している場合、宿泊費や交通費以外に「日当」として支給される出張手当があるかもしれません。支給基準や金額を確認し、適用できる出張があれば積極的に申請しましょう。
3. 福利厚生をフル活用するためのポイント
福利厚生を最大限に活用するには、企業が提供する制度を正しく理解し、自分の状況に応じた適用可能なものを把握することが重要です。以下のポイントを押さえて、見落としなく利用しましょう。
3-1. 会社の福利厚生制度を確認する
福利厚生は企業ごとに異なり、新しい制度が追加されることもあります。社内の就業規則や福利厚生ガイドラインを確認し、どのような制度があるのか把握しておきましょう。特に、新卒時や転職時に確認した内容から変更されていることもあるため、定期的に見直すことが重要です。
3-2. 利用可能な手当を申請する
手当は申請しないと受け取れないケースが多いです。例えば、資格手当や出張手当、在宅勤務手当などは、条件を満たしていても申請を忘れていると支給されません。必要な書類を準備し、期限内に申請を行う習慣をつけましょう。
3-3. 給与明細や社内ポータルをチェックする
給与明細には、支給されている手当や控除項目が記載されています。手当が適用されているかどうかを確認し、もし受け取っていない場合は人事部門に相談しましょう。また、社内ポータルサイトや掲示板に、新しい福利厚生の案内が掲載されることもあるため、定期的に情報をチェックすることをおすすめします。
3-4. 会社の担当者に相談する
制度の内容が分からない場合や、適用可否が不明な場合は、人事部や総務部に問い合わせるのが最も確実な方法です。特に、細かい適用条件がある場合は、直接相談することで具体的な利用方法を知ることができます。
まとめ
福利厚生や手当は、企業が従業員の生活や働きやすさを支援するために設けた制度です。しかし、知らなかったり、申請しなかったりすることで、本来受けられる恩恵を逃してしまう可能性があります。
会社の制度を定期的に確認し、申請可能な手当は必ず利用することで、生活の負担を軽減し、より快適に働くことができます。 ぜひ、今回紹介したポイントを参考に、福利厚生をフル活用しましょう。
参考文献
- 国税庁「給与所得となるもの」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2508.htm - 厚生労働省「企業における福利厚生の実態調査」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000195482.html - 独立行政法人 労働政策研究・研修機構「福利厚生と従業員満足度」
https://www.jil.go.jp/research/kouhyou.html