老後の資産形成について考え始めたものの、「どの制度を選べばいいのかわからない」と悩む方は多いのではないでしょうか。企業型DC(企業型確定拠出年金)とiDeCo(個人型確定拠出年金)は、いずれも老後資金を準備するための制度ですが、仕組みやメリット・デメリット、利用できる人や拠出限度額などに違いがあります。本記事では、両制度の違いをわかりやすく整理し、実際の選び方や活用のポイントまで具体的に解説します。
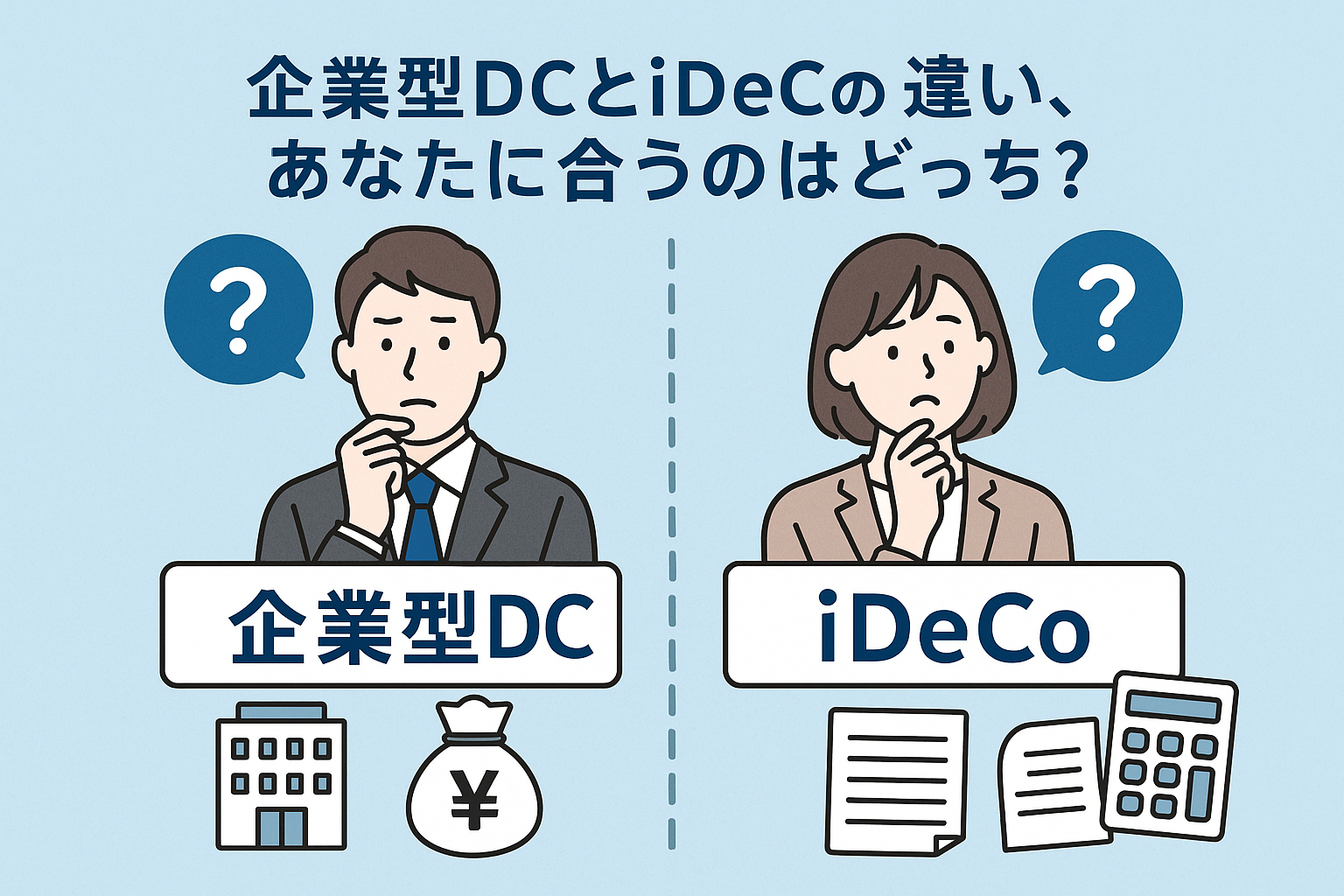
企業型DCとiDeCoの基本的な違い
まず、企業型DCとiDeCoはどちらも確定拠出年金制度ですが、成り立ちや利用できる人、運用方法などに明確な違いがあります。
企業型DC
企業型DCは、企業が従業員のために導入する退職金制度の一つです。企業が毎月一定額の掛金を拠出し、従業員がその資金を自分で運用します。原則として厚生年金被保険者である会社員が対象となり、加入や掛金の拠出は会社を通じて行います。運用商品は企業が選定した金融機関の商品から選ぶ形となり、手数料は原則として会社が負担します。掛金の上限は月額55,000円ですが、他の企業年金制度と併用している場合は上限が下がります。
iDeCo
一方、iDeCoは個人が自分の意思で加入する年金制度です。会社員だけでなく、自営業者、公務員、専業主婦(夫)など幅広い人が利用できます。掛金は個人が負担し、金融機関ごとに用意されている運用商品から自由に選んで運用します。手数料は個人負担で、掛金の上限は職業や他の年金制度の有無によって異なり、会社員の場合は月額12,000円または23,000円、自営業者は最大68,000円まで拠出できます。
どちらの制度も、積み立てた資産は原則60歳まで引き出すことができません。運用益は非課税で、受け取る際にも一定の税制優遇があります。
企業型DCのメリット・デメリット
企業型DCのメリット
企業型DCは、会社が掛金を負担するため、従業員は自分で資金を用意しなくても資産形成が始められます。掛金や運用益が非課税となり、受取時にも退職所得控除や公的年金等控除が適用されます。社会保険料の算定基礎に含まれないため、手取り収入や社会保険料への影響が少ない点も特徴です。
企業型DCのデメリット
一方で、企業型DCは運用商品が会社の選定したものに限られ、個人の希望通りの商品を選べない場合があります。また、規約によっては掛金額が制限されることもあります。原則として60歳まで資産を引き出せないため、急な資金需要には対応できません。運用次第では元本割れのリスクもあり、運用管理機関を選べない点もデメリットです。
iDeCoのメリット・デメリット
iDeCoのメリット
iDeCoは、個人が自由に金融機関や運用商品を選択できるため、全世界株式ファンドなど幅広い選択肢から自分に合った運用が可能です。掛金の全額が所得控除の対象となり、強力な節税効果が得られます。運用益も非課税で、受取時にも税制優遇があります。転職や退職、引っ越しなどライフスタイルの変化があっても、継続して積み立てができる点も大きなメリットです。
iDeCoのデメリット
iDeCoは、毎月の手数料が発生し、年間2,000~6,000円程度の管理コストがかかります。積み立てた資産は原則60歳まで引き出せず、途中解約はできません。運用商品によっては元本割れのリスクもあります。また、掛金の上限額は職業や他の年金制度の加入状況によって異なり、会社員の場合は企業型DCの有無によって制限されることがあります。
企業型DCとiDeCoの併用について
2022年10月以降、企業型DCとiDeCoの併用が可能となりました。企業型DCの掛金が少ない場合や、希望する運用商品が企業型DCにない場合は、iDeCoを併用することで老後資金をより手厚く準備できます。ただし、併用時は掛金の合計が上限を超えないよう注意が必要です。マッチング拠出が可能な企業型DCの場合、会社の制度内容によってはiDeCoよりもマッチング拠出の方がメリットが大きい場合もあります。
どちらを選ぶべきか?診断フローとケーススタディ
自分に合った制度を選ぶためには、勤務先の制度有無や掛金額、年収、ライフプランを総合的に判断することが重要です。
まず、勤務先に企業型DCが導入されているか確認しましょう。企業型DCがあり、会社の拠出額が十分であれば、まずは企業型DCを最大限活用するのが基本です。会社の拠出額が少ない場合や、さらに積み立てを増やしたい場合はiDeCoの併用を検討します。勤務先に企業型DCがない場合や自営業者、公務員、専業主婦(夫)の場合は、iDeCoをメインに利用することになります。
例えば、大企業に勤める30代の会社員の場合、企業型確定拠出年金(DC)で会社からの拠出金と自身の拠出金を合わせて月額55,000円積み立て、さらにiDeCoで月14,400円を積み立てることで、節税効果と老後資金の両方を効率よく強化できます。
個人事業主の40代であれば、iDeCoで月68,000円の上限まで拠出し、小規模企業共済も併用することで、複数の節税策を組み合わせた資産形成が可能です。
転職を検討している20代の場合、企業型DCの自己拠出が少ないケースでは、iDeCoで月23,000円を積み立てることで、転職やライフスタイルの変化にも柔軟に対応できる自由度の高い資産運用が実現します。
このように、それぞれの立場や働き方に応じて、企業型DCやiDeCo、小規模企業共済などを組み合わせることで、節税と資産形成の両立が目指せます。
失敗しない制度選びのポイント
1つ目は、手数料コストを意識することです。企業型DCは会社負担が多いものの、運用商品によっては手数料がかかります。iDeCoはすべて自己負担となるため、金融機関選びや商品の手数料も確認しましょう。
2つ目は、ライフイベントやキャリアプランに合わせて制度を選ぶことです。転職や独立の予定がある場合は、iDeCoを中心に設計することで、制度の継続性や資産の移換がしやすくなります。大企業に長く勤める予定であれば、企業型DCを最大限に活用するのが効率的です。
3つ目は、自身のリスク許容度を見極めることです。若い世代はリスク資産(外国株式ファンドなど)も積極的に活用し、リタイアが近い世代は安定運用の商品を選ぶなど、年齢や資産状況に応じて運用方針を調整しましょう。
まとめ
企業型DCとiDeCoは、どちらも将来の自分にとって大きな資産となる制度です。勤務先の制度内容や自身のライフプラン、リスク許容度を踏まえ、最適な方法で老後資産形成を始めましょう。まずは勤務先の企業型DCの規約を確認し、iDeCo口座の開設や積み立ての準備を進めることが第一歩です。少額からでも始めることで、将来の安心につながります。
なお、資産運用は自己責任で行う必要があります。制度や商品の内容をよく理解し、自分に合った方法で計画的に取り組みましょう。
【参考文献】
- 厚生労働省 確定拠出年金制度ガイドライン
- SBI証券 iDeCo比較資料
- はぐくみ企業年金ナビ「企業型DCとは」
- 野村アセットマネジメント「運用商品ラインアップの見方」
- 楽天証券「iDeCo・企業型DCの最新情報特集」





