「なんでこんなミスしたんだろう…」と、 誰しも一度は、そんな自己嫌悪に陥ったことがあるのではないでしょうか?
業務上のヒューマンエラー、たとえば「確認漏れ」「入力ミス」「手順違い」などは、一見すると注意力不足や意識の低さに原因があるように思われがちです。
しかし、近年の認知科学の知見では、こうしたエラーの多くが情報処理資源の過負荷といって、脳の処理能力が限界を超えていた状態で発生していると説明されています。
本記事では、ヒューマンエラーの背後にある脳の仕組みに注目し、「個人の努力では防げないエラー」がどうして起きるのか、そしてどう防ぐのかを科学的に解説します。
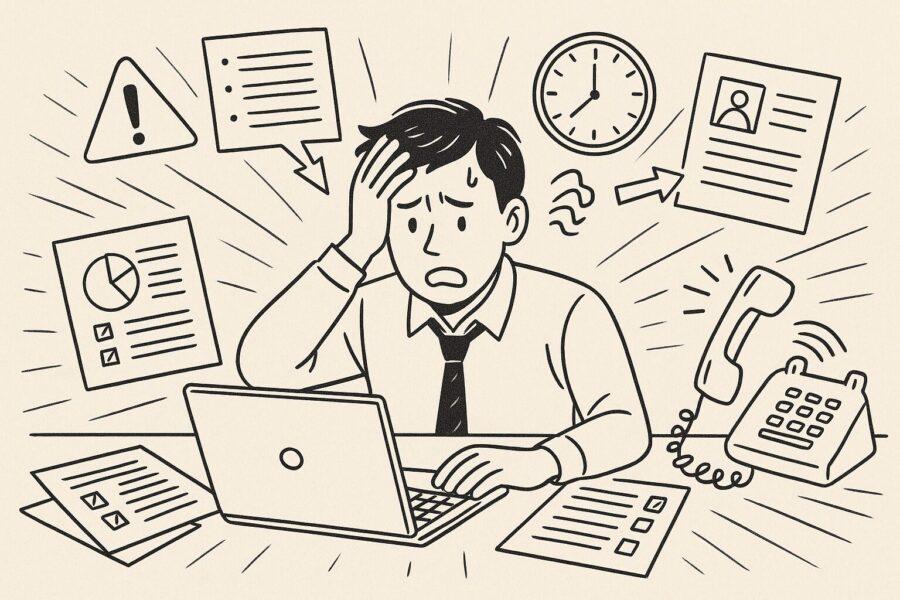
1.ヒューマンエラーは“人のせい”ではない
ヒューマンエラーとは「人が原因のミス」と思われがちですが、近年の研究では、脳の構造的な限界で、特に情報処理資源の枯渇によって引き起こされる現象であることが明らかになってきました。
よくある例として、「いつも通りの手順で作業したのに一部を飛ばしてしまった」「複数の作業に追われていたら、大事な返信を忘れた」といった経験はないでしょうか。これは注意力の低下というより、処理資源がオーバーフローした結果です。
ヒューマンエラーには主に3種類があり、それぞれ異なる過程で発生します。
1つ目はスリップ(Slip)です。これは知識や意図は正しいのに、操作上のミスが生じることを刺します。
2つ目はラプス(Lapse)です。これは記憶抜けにより、実行が漏れてしまいます。
3つ目はミステイク(Mistake)です。判断自体が誤っていることを刺します。
また、ミスの多くは新人ではなく、慣れたベテランによって起こることも珍しくありません。これは、習慣化した処理が無意識化され、かえって抜け落ちに気づきにくくなるためです。
実際、航空事故や医療事故でも、知識と経験を兼ね備えた人物によるヒューマンエラーが数多く報告されています。つまり、「エラーを防ぐこと」よりも「エラーを前提とした構造づくり」が本質的な対策なのです。
2.情報処理資源の正体と脳のキャパシティ
情報処理資源とは、脳が「考える・覚える・判断する」といった作業を行う際に使うリソースのことです。特に中心となるのが、前頭前野と呼ばれる脳領域であり、論理的思考や計画、意思決定を担っています。
この領域は非常に高機能である一方、エネルギー消費が激しく、長時間の使用には向いていません。とくに午後になると前頭前野の機能が低下し、判断ミスやケアレスミスが増える傾向があります。
脳の情報処理には3段階があります。
最初は選択で、何に注意を向けるかを決めます。次は保持で短期的に情報を記憶し、最後は抑制で不必要な情報を排除する仕組みになっているのです。
このうち「抑制」の機能が弱まると、周囲の雑音やスマホ通知に注意が奪われ、集中が続かなくなります。たとえば、仕事中にチャット通知が頻繁に届くと、そのたびに脳の処理が中断され、再集中までに膨大なエネルギーが必要になるのです。
また、作業記憶(ワーキングメモリ)は5〜9個程度の情報しか同時に保持できません。これを超えると情報があふれ出し、抜けや漏れが発生します。つまり、脳の処理キャパシティを理解し、それを超えないようにすることが、ヒューマンエラーを防ぐ鍵になります。
3.認知過負荷が引き起こすミスの構造
認知過負荷とは、「処理できる情報量を脳が上回ってしまう状態」のことです。注意力、記憶力、判断力のすべてがフル稼働している状態では、ミスをしやすくなります。
たとえば、医療現場では、夜勤中の看護師が複数の患者への投薬を一度に管理する際、誤投薬が起きやすいことが知られています。これは並列処理のしすぎによる認知過負荷が原因です。
教育現場では、授業中に複数の生徒の質問に応じながら板書を進めると、情報整理が追いつかず指示ミスが起きやすくなります。家庭でも「火にかけた鍋を忘れて、洗濯物を干していたら焦がしてしまった」など、身近なスリップはすべて認知過負荷の延長線上にあります。
また、人間の集中力には時間的制限があります。平均して20〜30分が限界とされており、それ以上の作業には定期的な休憩が必要です。これに基づいて「25分作業+5分休憩」を1セットとするポモドーロ・テクニックが、脳の処理リズムに合った作業法として評価されています。
4.過負荷を防ぐための現実的アプローチ
ヒューマンエラーを完全にゼロにすることは現実的ではありません。しかし、エラーが「起きにくい環境」を整えることは十分可能です。その鍵となるのが、認知資源(脳の処理能力)を無駄に消耗させない設計です。
たとえば、スマートフォンやパソコンの通知機能は、私たちの注意資源を断続的に分断します。これに対して、通知を受け取る頻度を意識的に制限し、たとえば1日に3回程度にまとめて確認するようなルールを設けることで、集中力の断片化を防ぐことができます。
また、判断の回数を減らす工夫も重要です。特に重要な意思決定は、脳が比較的フレッシュな朝の時間帯にひとつ、昼にもひとつまで、といった制限を設けることで、脳の疲弊を防ぎ、判断の質を保つことができます。
視覚情報の整理も、認知負荷を下げる上で有効な手段です。たとえば、1画面に表示する情報を3ブロック以内に抑えることで、脳の情報処理を助け、全体像の把握がスムーズになります。情報が散らかっていると、それを読み解くだけで注意資源を消耗してしまうため、レイアウトの整備は見た目以上に効果的なのです。
さらに、AIチャットボットやオートメーション機能の導入も、判断の機会を減らす上で大きな助けになります。人間が判断しなければならない場面を減らすことで、残された判断資源をより重要な意思決定に集中させることができるからです。
こうした個人レベルの工夫に加えて、組織として取り組むべき課題もあります。とりわけ大切なのは、「ミスは個人の責任ではなく、構造の問題かもしれない」という視点を持つ文化です。エラーが発生したとき、「なぜそんなことをしたのか?」と個人を責めるのではなく、「なぜそうせざるを得ないような環境だったのか?」と問い直す姿勢が、真の改善につながります。これは、個人にプレッシャーをかけるよりもはるかに生産的で、再発防止にもつながる考え方です。
5.まとめ
ヒューマンエラーの根本原因は、注意力や意識の問題ではなく、情報処理資源の過負荷にあります。現代の情報社会では、脳が一度に扱える情報量をはるかに超えた刺激にさらされることが日常化しています。こうした構造に気づき、エラーの“責任”を個人に押しつけるのではなく、情報環境や業務フローそのものを見直すことが求められます。人間の脳は有限であるという前提に立ち、負荷を減らすことで、エラーは自然と減っていくのです。
参考文献
- Wikipedia–Informationoverload
https://en.wikipedia.org/wiki/Information_overload - PubMed–Informationoverloadsyndrome:abibliographicreview
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34877645/ - ComplianceOnline–HumanErrorandCognitiveLoad
https://www.complianceonline.com/human-error-and-cognitive-load-webinar-training-704210-prdw - MayoClinicHealthSystem–Cognitiveoverload
https://mayoclinichealthsystem.org/hometown-health/speaking-of-health/cognitive-overload - EuropePMC–Dealingwithinformationoverload:acomprehensivereview
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10322198/ - ResearchGate–Contributionsofcognitiveloadtheorytounderstandinginformationoverload
- ScienceDirect–Causes,consequences,andstrategiestodealwithinformationoverload
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667096824000508





