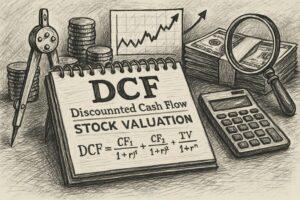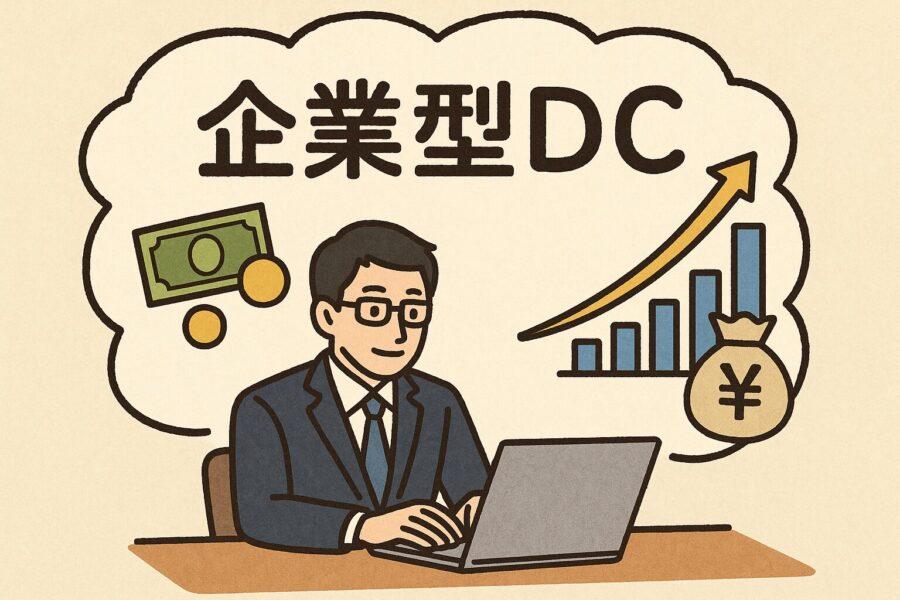
将来の年金額が不安視される今、「企業型DC(企業型確定拠出年金)」という言葉を耳にする機会が増えました。とはいえ、「会社でやってるらしいけど自分に関係あるの?」「何か運用しなきゃいけないって面倒くさそう」というイメージを抱いている方も多いかもしれません。
本記事では、企業型DCの仕組みや税制メリット、実際に導入している企業の事例、さらに個人型iDeCoとの違いまで、サラリーマン視点でわかりやすく解説します。“老後資金は自分で作る時代”に備えるための第一歩として、ぜひご活用ください。
1.企業型DCの仕組みを理解しよう
企業型DCとは、企業が掛金を拠出し、従業員がその資金を運用して老後の年金を準備する制度です。厚生労働省によれば、2024年3月末時点で企業型DCの導入企業数(規約数)は7,222件、加入者数は約830万人となっており、前年同時期(2023年3月末、805万人)と比べて25万人増(+3.1%)という着実な伸びを示しています。資産残高も22兆7,061億円と、前年より約3.96兆円増加(+21.2%)しており、企業型DCの規模と利用者の急拡大が続いています。
この制度は、従来の退職金制度や厚生年金とは異なり、運用リスクもリターンも従業員自身に帰属します。企業は毎月、決まった掛金を支払い、従業員は用意された金融商品(たとえば定期預金や国内外の投資信託など)から選んで運用するのが特徴です。
運用商品には元本確保型(定期預金や保険商品)とリスク型(株式投信など)があり、選択の自由度が高い一方で、従業員の金融リテラシーによって将来の年金額に大きな差が生じる可能性もあります。
実際、2020年度の企業型DC(確定拠出年金)に関する調査では、加入者の平均資産残高は制度全体で約212万円と報告されています。
また、定年退職前にあたる50代ではその平均が約408万円にまで達しており、長期間にわたる拠出・運用による資産形成の幅がうかがえます 。
たとえば楽天グループでは、従業員にリスク型投信を推奨し、資産形成教育にも力を入れています。資産運用に不慣れな新入社員を対象にしたオンライン研修を行うなど、投資教育の実施も進んでいるのです。
2.企業型DCの税制メリットと活用法
企業型DCの大きな魅力は、税制優遇にあります。また、会社が拠出するため、自分の財布を痛めずに資産形成できる点も大きなポイントです。
企業が拠出する掛金は、給与として課税されず所得税や住民税の対象外です。さらに、運用で得た利益も非課税となり、通常の金融商品であれば20.315%課税されるところが免除されるため、長期で見れば税金の差は数十万円以上に及ぶ可能性があります。
たとえば年収500万円の会社員が月額2万円(年24万円)の掛金を企業型DCで積み立てている場合、所得税率10%、住民税10%と仮定すると、年間で約4.8万円の節税効果がある計算になります。
さらに、企業によっては従業員が自己資金を上乗せする「マッチング拠出制度」を導入しているところもあります。たとえばNTTグループやソフトバンクでは、一定の自己拠出に対して会社も追加で拠出する仕組みが整備されており、これは企業から“お金のプレゼント”を受けているようなもので、活用しない手はありません。
2024年度時点では、企業型DC導入企業のうち51.9%がマッチング拠出を採用しており、導入比率は甦りつつも高水準で定着しています。実際に利用している従業員は導入企業内で約35%に留まり、まだ伸びしろがあります。
また、2025年度の税制改正案では、企業型DCとiDeCoを合わせて月額6.2万円まで拠出可能となる見込みで、マッチング拠出もさらに使いやすくなる予定です。これにより、制度利用は今後ますます拡大が期待されています。
さらに、企業型DCで積み立てた資産は、転職や退職時に6ヶ月以内に「iDeCo」や新職場の企業型DCに移換が必要です。移換を怠ると自動移換となり、手数料(3,300円+1,048円+月52円など)が累積し、運用停止、税制優遇停止、老齢給付金受け取りの遅れなどのデメリットが生じます。
3.iDeCoとの違いと併用時の注意点
企業型DCと混同されがちな制度に「iDeCo(個人型確定拠出年金)」があります。両者は仕組みが似ているようで実は大きく異なります。
企業型DCは企業(と場合によっては従業員)が掛金を出す制度であり、原則としてその企業の正社員や契約社員が対象となります。一方、iDeCoは完全に個人が拠出する年金制度であり、職業に関係なく原則誰でも加入可能です。企業型DCの拠出上限は月額5.5万円程度であるのに対し、iDeCoは職業に応じて月額2.3万円から6.8万円までと定められています。
企業型DCに加入していても、企業側が「iDeCo併用可」にしている場合は、個人でもiDeCoに加入することができます。ただしその場合、拠出限度額は月額2万円に制限されることが多く、制度によっては併用できないこともあるため、自分の会社がどの制度を導入しているか、併用可能かどうかは必ず人事部に確認しておくことが大切です。
ちなみに、iDeCoは2017年以降加入対象が拡大され、専業主婦や公務員も加入できるようになりました。これにより、夫婦での年金形成を計画的に進める家庭も増えています。
まとめ
企業型DCは、会社が用意してくれる非課税で積み立てができる極めて有利な制度です。しかし、その恩恵を受けられるかどうかは、自分が制度を理解し、行動するかにかかっています。
特に、自社に制度はあるが放置している方、運用商品を長年変更していない方、転職後に資産移換をしていない方、税制メリットを活かせていない方などは要注意です。老後2,000万円問題と言われる今、“知らないこと”が損失につながるかもしれません。
まずは自分の勤務先が企業型DCを導入しているかどうか確認し、制度内容を見直してみましょう。未来の安心は、今日の行動から始まります。
出典一覧
国税庁|所得税・住民税の仕組み
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm
国民年金基金連合会|iDeCo公式サイト
https://www.ideco-koushiki.jp/
野村證券|企業型DCとiDeCoの違い
https://www.nomura.co.jp/retail/saving/ideco/dc.html
楽天証券|DC制度と税制メリット
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/special/dc/