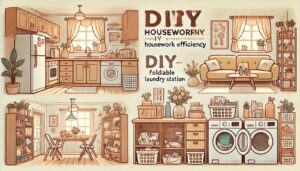社会保険料は、給料から毎月天引きされるため、意識せずに支払っている人も多いでしょう。しかし、年間で見ると大きな金額になり、家計を圧迫する原因にもなります。特に、手取りがなかなか増えないと感じている人は、この負担の重さを実感しているかもしれません。
そこで、本記事では社会保険料の仕組みや、負担を減らす具体的な方法を解説します。社会保険料の負担を抑えることで、手取りを増やし、将来の資産形成につなげることも可能です。最後まで読んで、実践できる節税対策を見つけてください。
1. 社会保険料が家計を圧迫?負担の仕組みと節税の基本
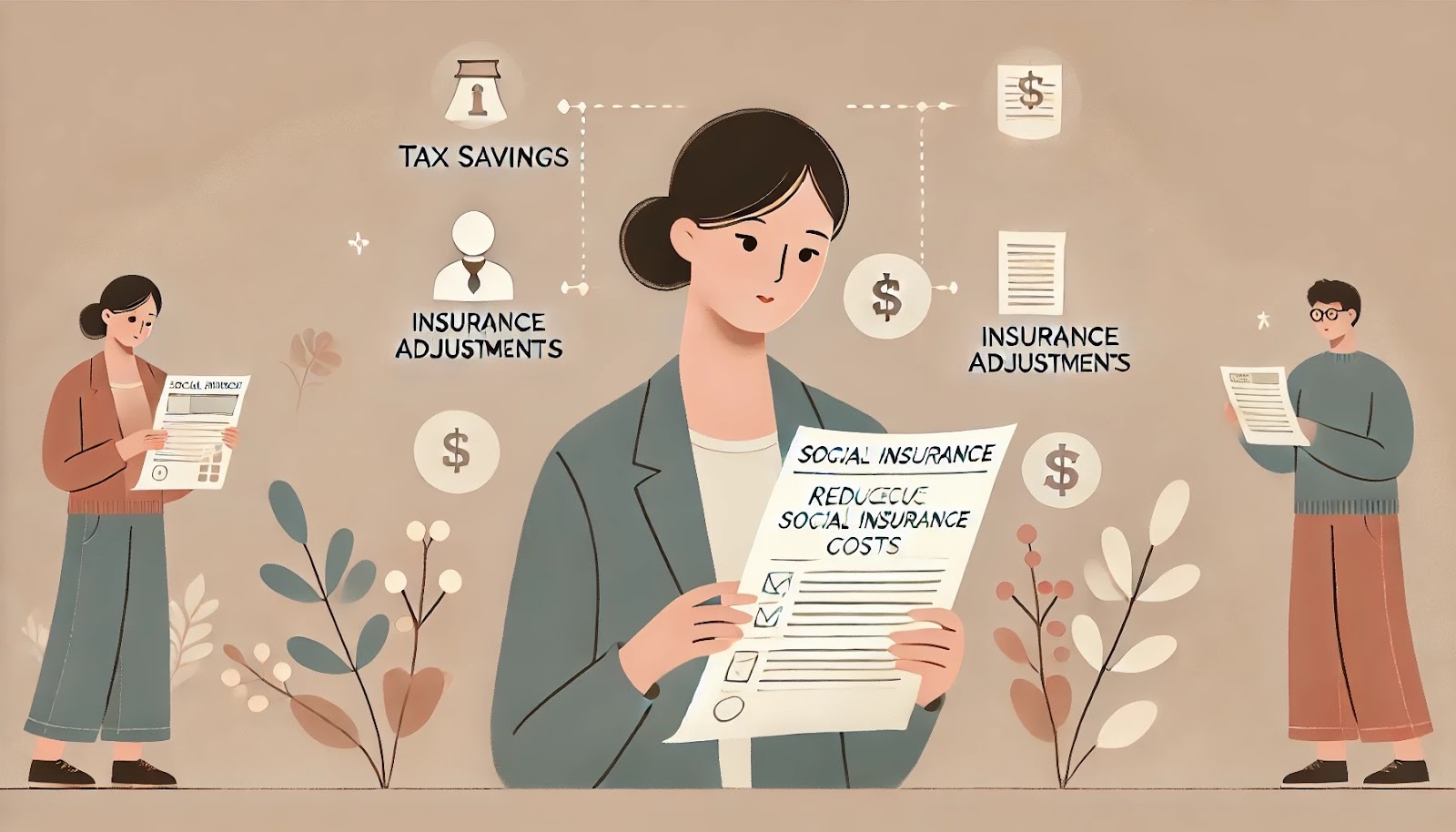
1.1社会保険料の内訳とは?
社会保険料には、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料などが含まれます。会社員であれば、会社が半分を負担しているものの、給与の約15%が社会保険料として引かれています。さらに、企業側も同額を負担しているため、トータルで給与の約30%が社会保険料として支払われている計算になります。
自営業者やフリーランスの場合は、国民健康保険と国民年金に加入する必要があり、所得に応じた負担が発生します。会社員と異なり、個人で全額を負担しなければならないため、特に社会保険料が重くのしかかるケースが多いです。
1.2なぜ社会保険料は高いのか?
社会保険料の計算は、基本的に所得に応じて決まります。特に、厚生年金や健康保険の保険料は、4月〜6月の給与をもとに標準報酬月額が決まり、その後1年間固定される仕組みになっています。つまり、この期間の給与が高いと、それ以降の社会保険料も高くなるというわけです。
また、日本の社会保険制度は「現役世代が高齢者を支える」という仕組みになっているため、少子高齢化の影響で負担が増加し続けています。
1.3節税と手取りアップの基本
社会保険料の負担を減らすには、合法的な手段を活用しながら、適切に対策を講じることが求められます。具体的には、給与の設定や手当の見直し、働き方の調整などが有効です。社会保険料を適正に抑えることで、手取り収入を増やし、より賢くお金を管理できるようになります。
2. 社会保険料を抑えるための具体的な方法
2.1 4月〜6月の給与の調整
社会保険料は、毎年4月〜6月の給与の平均額をもとに計算されます。このため、この期間に残業や手当が多くなると、社会保険料が増加する可能性があります。例えば、残業時間をこの3カ月間だけ減らす、または賞与ではなく他の手当で調整するなどの工夫が考えられます。
また、昇給のタイミングも重要です。昇給が4月〜6月に行われると、そのまま標準報酬月額が引き上げられ、社会保険料の増額につながる可能性があります。可能であれば、昇給のタイミングを7月以降にずらすことで、負担を抑えられます。
2.2 賞与の支給方法を工夫する
賞与も社会保険料の計算対象になりますが、一般的に賞与にかかる保険料は給与とは別で計算されます。そのため、社会保険料の負担を抑えたい場合は、賞与の支給を抑え、その分を福利厚生として支給する方法が考えられます。例えば、社員のスキルアップのための研修費用を会社が負担する、社宅や通勤手当を充実させるといった形で補填すると、実質的な手取りを増やしながら社会保険料の増加を抑えることが可能です。
2.3 福利厚生を活用する
社会保険料の対象となる給与には含まれない「福利厚生」を活用することで、負担を減らせるケースがあります。例えば、食事補助や住宅手当、資格取得補助など、給与に直接反映されない形での支給が有効です。会社側にとっても、福利厚生を充実させることで従業員の満足度が向上し、長期的な人材確保につながるメリットがあります。
2.4 退職金を活用する
給与として支給されると社会保険料の対象になりますが、退職金として支給される場合は社会保険料がかかりません。そのため、長期的な視点で考えると、一部の報酬を退職金として積み立てることで、社会保険料の負担を減らすことが可能です。ただし、退職金制度の導入には企業側の対応が必要なため、事前にルールを確認しておきましょう。
3. マイクロ法人活用のメリットと注意点
3.1マイクロ法人とは?
マイクロ法人とは、法人として設立するものの、従業員を雇わずに一人で運営する小規模な会社のことです。個人事業をそのまま法人化するのではなく、「個人事業と法人の両方を活用する」という形を取ることで、社会保険料の負担を大幅に軽減できるメリットがあります。特に、社会保険料の節約を考えるなら、法人と個人の二刀流を戦略的に活用することが重要です。
3.2マイクロ法人を活用するメリット
この仕組みを活用すると、個人事業の収入はそのまま維持しつつ、マイクロ法人の報酬額を低く抑えることで、社会保険料の負担を最小限にできます。具体的には、役員報酬を一定の範囲内に抑えることで、健康保険や厚生年金の負担額を軽減し、国民健康保険や国民年金と比較してコストを抑えられる点が魅力です。また、法人化することで、経費として計上できる範囲が広がるため、節税効果も期待できます。
3.3マイクロ法人の注意点
ただし、この仕組みを利用する際にはいくつかの注意点があります。まず、法人の維持には一定のコストがかかるため、社会保険料の節約効果と比較してバランスを考える必要があります。また、法人の売上と個人の収入の振り分けを適切に行わないと、税務署や年金事務所の調査対象となるリスクもあるため、慎重に設計することが求められます。
4. 社会保険料を抑えるだけでなく、将来の資産形成も考えよう
4.1将来のための資産運用
社会保険料を抑えることは、手取り収入を増やすうえで非常に有効ですが、単純にコストを削減するだけではなく、将来の資産形成にも目を向けることが重要です。例えば、社会保険料の負担を減らすことで生まれた余剰資金を、資産運用に回すことで、将来的な経済的な安定につなげられます。
具体的には、iDeCoやNISAを活用することで、将来の年金対策をしながら税制優遇を受けることが可能です。特にiDeCoは、掛け金が全額所得控除の対象となるため、節税しながら老後資金を準備するのに適した制度です。
4.2老後資金と社会保険料のバランス
社会保険料を抑えることばかりに気を取られてしまうと、将来受け取る年金額が減少するリスクもあります。特に、厚生年金の加入期間が短くなったり、標準報酬月額が低くなったりすると、受給額が減ってしまうため、長期的な視点で考えることが必要です。
また、健康保険の負担を減らした場合、将来の医療費負担が増える可能性もあります。たとえば、傷病手当金や高額療養費制度の恩恵を受けにくくなるケースもあるため、安易に削減しすぎるのではなく、自分のライフプランに合わせて適切な対策を講じることが大切です。
5. まとめ
社会保険料は、毎月の手取りを大きく左右する重要なコストですが、工夫次第で負担を抑えることが可能です。給与の調整やマイクロ法人の活用、福利厚生の充実など、さまざまな手段を組み合わせることで、賢く節税しながら手元に残るお金を増やすことができます。
節税と資産形成を両立させ、将来に向けてより安心できるライフプランを築いていきましょう。
参考文献